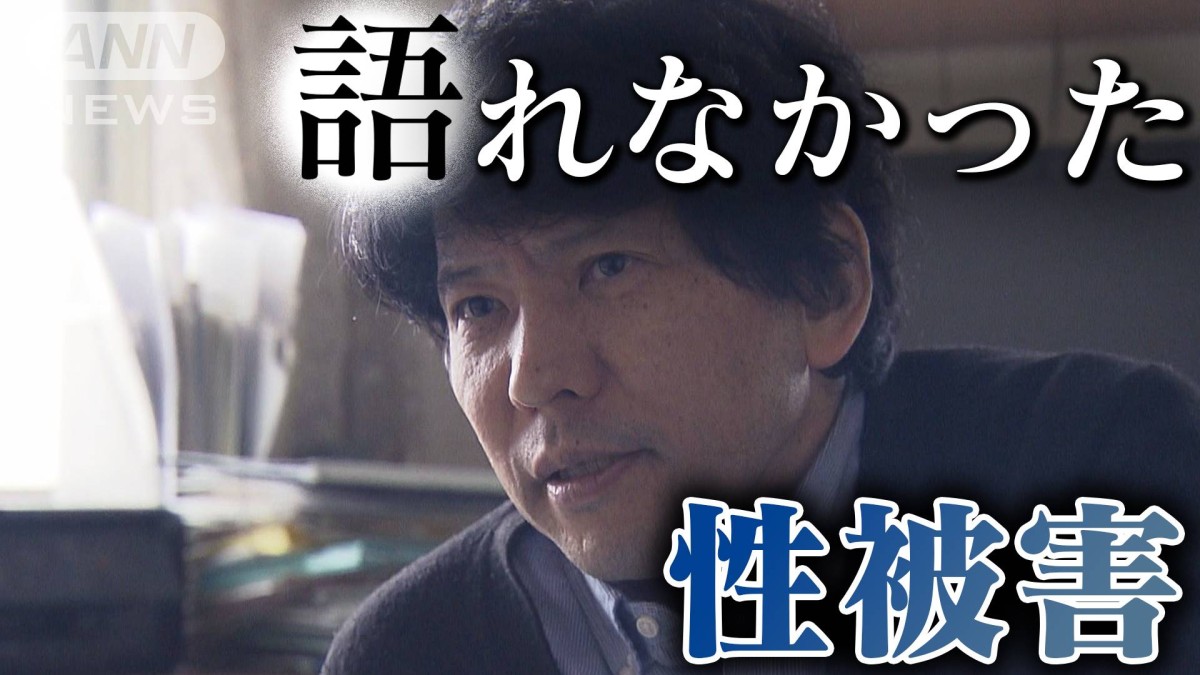「誰も男性性暴力被害者について理解できる人がいない」今も抱えるそんな思いを、カメラの前で明かしてくれた。
福岡県に住む菊永拓郎さん(取材当時50歳)は、留学先のイギリスで受けた性暴力の記憶に苦しめられてきた。女性と比べて表面化しづらいとされる男性の性被害。国が初の実態調査に乗りだし、法律の改正も進む。機運が高まるいま、当事者や支援の現場を取材すると「表面化しづらい理由」が見えてきた。
※性暴力被害の実態を伝えるため、被害の詳細について触れています。フラッシュバックなど症状のある方はご留意ください。
(テレビ朝日 社会部記者 松本拓也)
■ 「家族や友人に話せず孤独だった」 寝る前には“トラウマ記憶”が蘇り…
「ああ、一体どこなんだ、どこへ行ってしまったんだ、俺の過去は。俺が若くて、快活で、頭がよかったあの頃は。俺が美しい空想や思索にふけったあの頃。俺の現在と未来が希望に輝いていたあの時代は、どこへ行ったのだ」演劇の稽古の一幕に引き込まれた。それまでとは顔つきが一変したためだ。去年12月、福岡県の貸しスタジオ。菊永拓郎さんは、演技に没頭している時だけは苦しみが和らぐと打ち明けてくれた。
自分で脚本を書きながら演劇活動をしている菊永さん。その一環でイギリスに留学した2001年、29歳の時のこと。そこで男性から性暴力を受ける。相手はホームステイ先を訪ねてきた、ホストマザーの弟だった。「向こうはマッサージと言っていたが、明らかに性的な接触みたいな感じで、胸から触られて順々にそれがお腹の方に降りてきた」20分以上抵抗を続けた。一瞬、相手の力が弱まった隙に何とか逃れることができた。ホストマザーに被害を訴えたが、相手にしてもらえず家を追い出されたという。
「怖かったし、今考えても恐ろしい体験だった」留学先のイギリスでは当時、助けを求められる人が誰もいなかったと振り返る。寝る前になると被害にあった場面が脳裏に浮かんだ。恐怖体験によってもたらされる心の傷=トラウマに何年も苦しみ、帰国後に受診した医療機関で心的外傷後ストレス障害=PTSDと診断された。イギリスの警察に被害届も出したが、時間が経っていたため「証拠がない」と相手にしてもらえなかった。
「自分の家族や友人にほとんど話せず、孤独だったのが一番辛かった」なぜ、被害を明かせなかったのか。そう質問すると、すぐに答えが返ってきた。「『男性は被害を受けない』とか。『被害を受けても相談すべきではない』とか。『男性は強くないといけない』といった偏見が社会にあることが原因だと思う。社会に男性も性暴力被害を受けるという認識がない」孤独の中で、たった独りもがいてきた。気が付けば22年の歳月が過ぎていた。
■ 相談は“氷山の一角”…支援の現場から見えた「表面化しづらい理由」
性犯罪の厳罰化を柱とした改正刑法が施行されたのは2017年7月のこと。強制性交罪などで、告訴を起訴の条件とする「親告罪」の規定も撤廃された。さらに、女性に限られていた被害者に男性も含まれるようになった。警察庁によると、全国の強制性交等事件の認知件数は18年以降、年間1400件前後で推移する。このうち男性の被害者は50〜70件前後で、全体の3〜5%ほどだ。割合こそ多くはないが、支援の現場を取材すると男性であるが故の難しさが垣間見えた。
日赤愛知医療センター名古屋第二病院の一角には、被害者への配慮から診療科の名前が書かれていない部屋がある。ここが性暴力救援センター日赤なごや「なごみ」の拠点。病院内に併設された性被害に特化した支援センターだ。SANE(セイン=性暴力被害者支援看護職)と呼ばれる性暴力被害者支援専門の看護師をはじめ、医師、支援員、医療ソーシャルワーカーたちが24時間対応にあたる。精神的なケアをはじめ、被害を受けた後、刑事事件化を見据えて証拠を採取し保存する手助けもしている。「なごみ」には相談の電話が絶えることがない。1日60件ほどの日もあるという。
取材をした日も電話が鳴った。酒を飲んで帰宅途中に面識のない男性に声を掛けられ家に連れていかれたあと、性行為をされたという女性からの相談だった。支援員が丁寧に状況を聞き取り、今後の対応についても相談に乗っていく。結局、この女性は直接相談に来ることになった。ただ、対面での面談にまで繋がるケースはそう多くないという。特に男性は数が少なく、2016年の「なごみ」開所以来、相談が159件、実際に面談まで漕ぎつけたのは27件だった。その理由を副センター長の山田浩史医師はこう説明する。
「女性の場合は妊娠というリスクがある。だから72時間以内に来所してくれる場合が多く、避妊のための処置ができる。一方、男性は妊娠のリスクがない。そのため来所が遅れ、物的証拠なり被害が実際にあったということを証明するような検体とかが取れない状態になってしまう」
男性の場合、身近な人から被害に遭うのも特徴だという。「実の父親から性暴力を受けた人、職場の上司から職を失わないためには自分の言うことを聞けと言われて被害を受けた人、出張の時に同じ部屋を取って上司から性暴力を受けた人などがこれまでに相談に来た」悩んだあげく相談をしてきた人は一握りで、「声を挙げられない人はたくさんいるはずだ」と山田医師は語る。
■ 男性の性暴力被害学ぶ機会が乏しい実態 国の初調査で課題が明らかに…
「被害者の職業別の欄に無職というのがあるが、これは被害を受けたことによって職を失った人たちです」東京で開かれた学会発表の場に、山田医師の姿があった。各地で男性性被害者の支援の現状について語る機会を設けている。1人でも多くの医師に男性被害者の診療にあたってもらいたいとの考えからだ。発表後に山田医師がこぼした言葉が印象的だった。「学会に参加しても発表はいつも最後の方で、聞いてくれる人も少ない。聞いてくれるのも、もともと支援にあたっている人などが多い。関わってくれる人が増えれば、もっと被害者が声を挙げやすくなるのに…」300人ほど入る会場だったが、空席が目立っていた。
2022年から国は男性や小児、性的マイノリティへの性被害に特化した初めての実態調査に乗りだしている。この調査でも受け皿となる医療機関などの課題が明らかになってきている。約2000の医療機関を対象にしたアンケートで「男性の性暴力被害について学んだ機会があるか」を聞いた。すると、「医学部時代に聞いたことがある」と答えたのは、すべての診療科で3%以下という結果になった。「学会や講演で聞いたことがある」と答えたのも、産婦人科で14%、小児科13.4%。救急科では5.8%、泌尿器科では2.4%だった。実際に診療をしたことがある医師はさらに少ないこともわかった。
調査を担う国の研究班代表で島根大学の河野美江教授は「まずは医療機関が見ますよと言わないと、被害者の方って絶対に病院に行かないと思う」と訴える。そのうえで「日本は海外と比べて40〜50年遅れている。男性や性的マイノリティなどへの被害はまだまだ認知されていない」と強調した。研究班は2024年度までに支援マニュアルの整備を目指している。
■ 性被害者支援で遅れをとる日本 先を行く海外の現状は?
海外に目を向けると男女を問わず性被害者への支援の取り組みは多岐に渡る。
国が被害者支援のマニュアルを整備している国もあれば、民間の支援団体に手厚く資金を援助している国もある。イギリスでは性被害者の支援に関わる「ISVA(イスバ)」と呼ばれる資格が存在する。被害にあった後、警察への報告や裁判の付き添い支援、その後のサポートもしてくれる専門家だ。日本でも、「ISVA」を導入できないかとの動きが出始めている。
イギリスで演劇の留学中に性暴力を受けた菊永拓郎さんは、日本ではなかなか自分にあった支援に巡り合うことができなかった。そのため、アメリカやイギリスの被害者回復プログラムに参加してきた。オンラインも含めると、その数は5回にわたる。被害にあった当事者やその家族、パートナーらと一緒に経験などを語り合った。「日本にもこういう場があれば…」自身の経験から、菊永さんは被害者がいち早く相談や治療に繋がることを願ってやまない。
取材も終盤に差し掛かった頃、疑問に思っていたことを聞いた。なぜ、実名で顔を出してまで取材に応じてくれたのか。「男性性暴力被害者がここにいるよということを社会に知ってほしかった」相談できる場がなく孤立したこと…。社会の無理解や偏見に苦しめられたこと…。被害者が1人でも声を挙げやすくなればと勇気を振り絞って語ってくれた。
同意がない性行為は犯罪になり得ることが明確になるなど、性犯罪の厳罰化がさらに進む。機運が高まるいま、当事者や被害者支援にあたる現場は社会の関心が高まることを強く望んでいる。
広告
1
広告