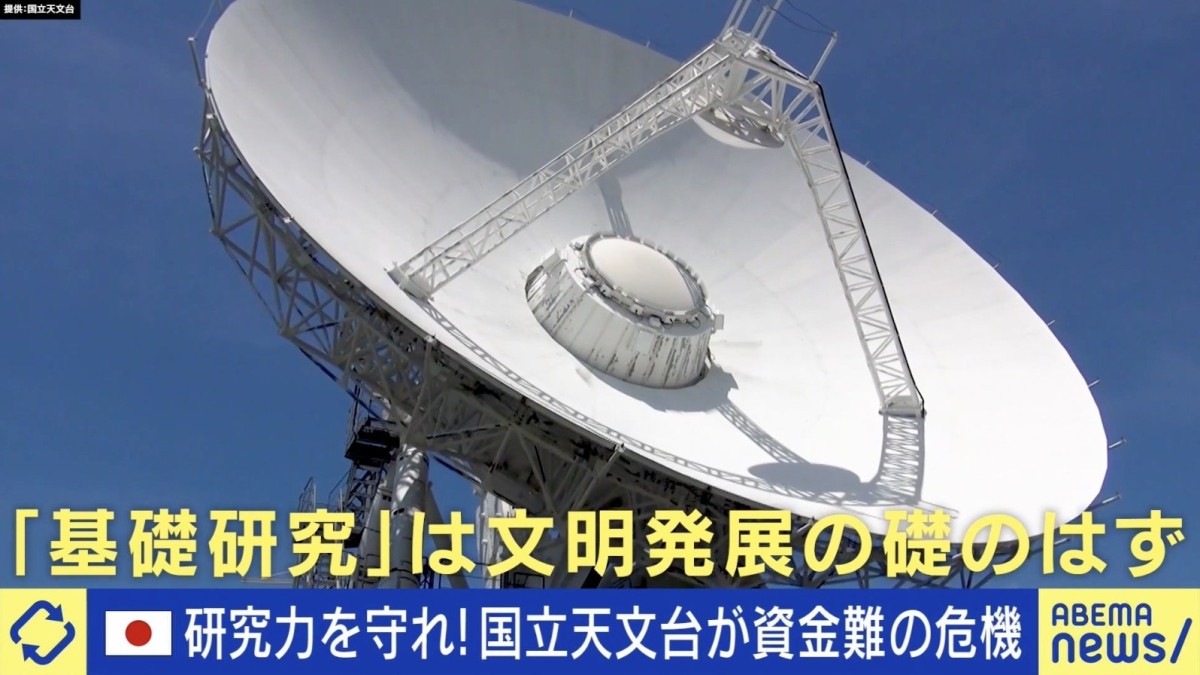岩手県にある国立天文台の観測所は、人類史上初となるブラックホールの撮影に貢献するなど、天文学の重要な研究拠点だ。また宇宙の美しさや不思議さを学べる場所としても、多くの人に愛されている。
しかし、10年前と比べて予算が半減し、資金不足に悩んでいるという。先日も、東京にある天文台本部が、SNSで「寄付」を呼びかけ、「国は何しているの」「ぜひ税金を使ってほしい」など、声を上げる人が続出した。
国立天文台や国立大学は、2004年に法人化されて以降、国からの交付金が減り、研究資金の確保が大きな課題になっている。そこに物価高や人件費の上昇など、さまざまな要因が追い打ちをかけているという。
そもそも天文学は、自然現象の原理などを探る「基礎研究」であり、すぐに実用化や利益にはつながらない。しかし、世の中を豊かにする科学技術は、根幹に基礎研究があるからこそ成り立つ。資金不足により人員削減が起きると、任期付きの若手研究者が対象になりやすい点も課題だ。
国立天文台では、クラウドファンディング挑戦などの打開策を打ち出しているが、ギリギリの状態が続いている。『ABEMA Prime』では、職員から資金不足の実情を聞くとともに、基礎研究の重要性について考えた。
■国立天文台とは?

国立天文台は、日本の天文学研究の拠点で、三鷹(本部)・水沢・野辺山・ハワイなどに100台以上の望遠鏡を所有している。大規模な観測施設を全国の研究者に提供する「共同利用機関」であり、運営財源は主に税金でまかなわれている。
国立天文台水沢VLBI観測所の本間希樹所長は、「共同利用機関には、私たちが大きな装置を運用して、天文学者や大学の先生に使ってもらう役割がある。自分たちの研究もするが、電波望遠鏡など、何十メートル級のものを作り、多くの人に使ってもらう役割を持つ。大きな望遠鏡がないと、新しい研究はできない」と説明する。
水沢で行われている“VLBI”は「電波望遠鏡を使ったプロジェクト」だという。「衛星放送のパラボラアンテナを巨大にしたものをイメージして欲しい。宇宙からの電波をアンテナでとらえて、いろいろな謎を明らかにする。天の川の地図を作ったり、ブラックホールを撮影したりしている」。
■資金難の現状

そんな業績を残す水沢VLBI観測所だが、資金難に見舞われている。背景には、そもそも国立天文台全体で、国からの「運営費交付金」が減少していることがある。その上で、天文台本部からの予算も、優先度の高いプロジェクトや施設に回される。加えて、電気代の高騰(望遠鏡など大型設備の運用には膨大な電力が必要)や人件費の上昇、為替レートの影響などがあり、10年で予算は半減となった(2015年の約4億円から、2025年は約2億円へ)。
本間氏によると、「国立天文台だけでなく、日本の基礎科学が厳しい問題に直面している。国からの運営費交付金が、少しずつ減っている。最終的に10年で半分になり、どうしようもない状態だ」という。
対応策としては「自動化により人員を減らしたり、メンテナンスを飛ばしたりしている。車でいう“車検”のように、アンテナも安全性に問題ないか確認しないと、時に止まってしまうこともある。それらをスキップすることで、予算を浮かしている」のだそうだ。
予算削減によって、人員面では「任期付きのポジションから減らすことになる。若手の研究者は、3年や5年契約なことも多いため、人員削減により若手が生き残れないのは大きな問題だ」といった懸念も抱えている。
■「予想もしない形で、きっと役に立てることがある」

そんななか、生き延びるための取り組みも行われている。財源の多様化で若手研究者を確保すべく、2022年にはクラウドファンディングに挑戦した(目標1000万円→結果3000万円超え)。また、企業と連携し、研究者を雇用してもらうことで、会社員として働きながら、研究者キャリアも継続するスタイルを模索している。世界と闘うための知恵やアイデア勝負として、予算のかかるハード面ではなく、ソフトウェア開発なども手がける。
クラウドファンディングで集めた資金の使途は、「半額程度を使って若手を雇い、ポジションが減った分を取り返そうとしている。いまは1人、この資金で雇用している研究者がいる」としつつ、「資金調達の見通しが立たず、やはり難しい。国だけに頼らず、各方面から資金を取るのが1つの解だろう」と説明する。
国の財政方針について、本間氏は「何がどう発展するか読めない基礎研究に、“選択と集中”はなじみづらい。科学を大きく発展させる大発見の芽は、いつ出るか予想できない。“選択と集中”では、どうしても結果が出やすいと予想されるものに偏る」と指摘する。
基本姿勢としては「僕らは好奇心で研究していて、何か利益につなげようとはしていない」と語る。「知ってもらうことが大事だ。天文学のおもしろさや、基礎科学の重要性を知ってもらえば、予想もしない形で、きっと役に立てることがある」。
(『ABEMA Prime』より)