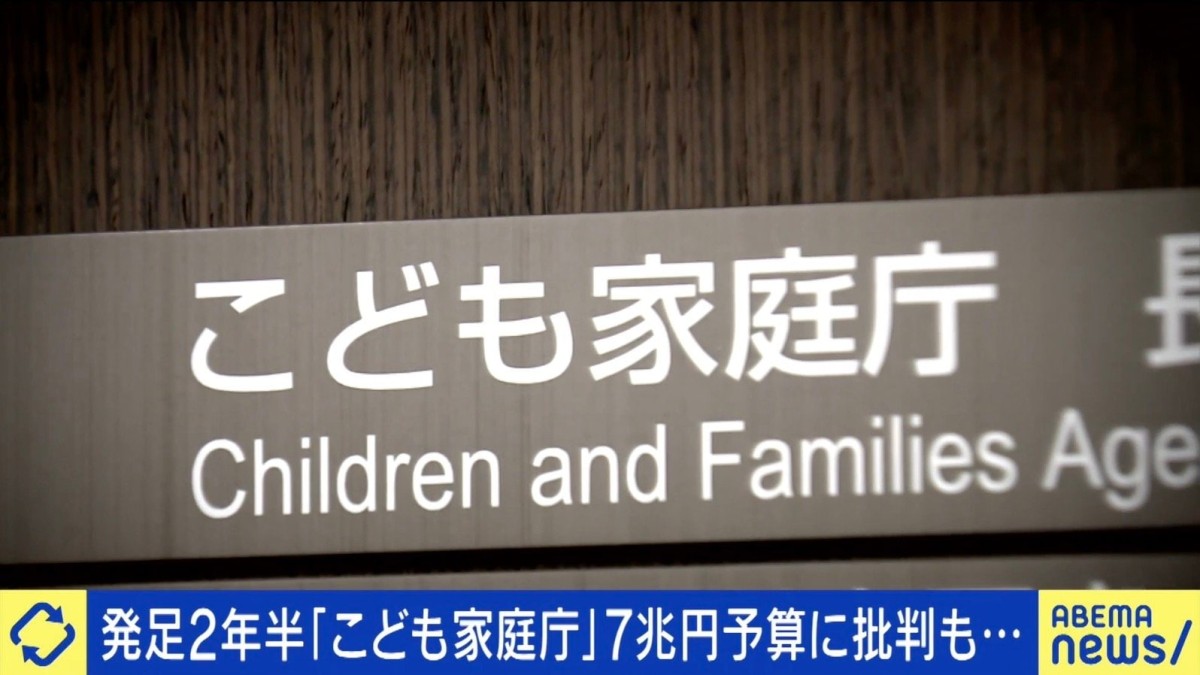こども家庭庁が先週、総額7兆4000億円を超える2026年度予算の概算要求をまとめた。
内訳では、保育所や放課後児童クラブの運営費、児童手当が半分以上を占め、育児休業などの給付に1兆600億円をあてるとした。また、性や妊娠・出産について正しい知識を付け、将来設計を考える「プレコンセプションケア」の普及に7億円を計上。さらに不妊治療などの支援や、クリニックが遠い場合の交通費助成なども盛り込んだ。
子育て支援が手厚くなりそうだが、Xでは「こども家庭庁の解体で7兆円の財源確保ができる」「その予算で子どもに1000万円ずつ配ればいい」などのように、少子化が改善しない中でふくらむ予算に批判が噴出している。
また、予算以外でも2026年4月から導入される「子ども・子育て支援金制度」が物議になっている。社会保険料の一部として国民から広く聴取されるにもかかわらず、恩恵が子育て世代に限られることから“独身税”などと、やゆされている。
子どものためだったはずのこども家庭庁が、なぜたたかれてしまうのか。『ABEMA Prime』では識者とともに、批判とその妥当性を考えた。
■「子どもの幸福を真ん中に据えて、施策を洗い出す必要がある」
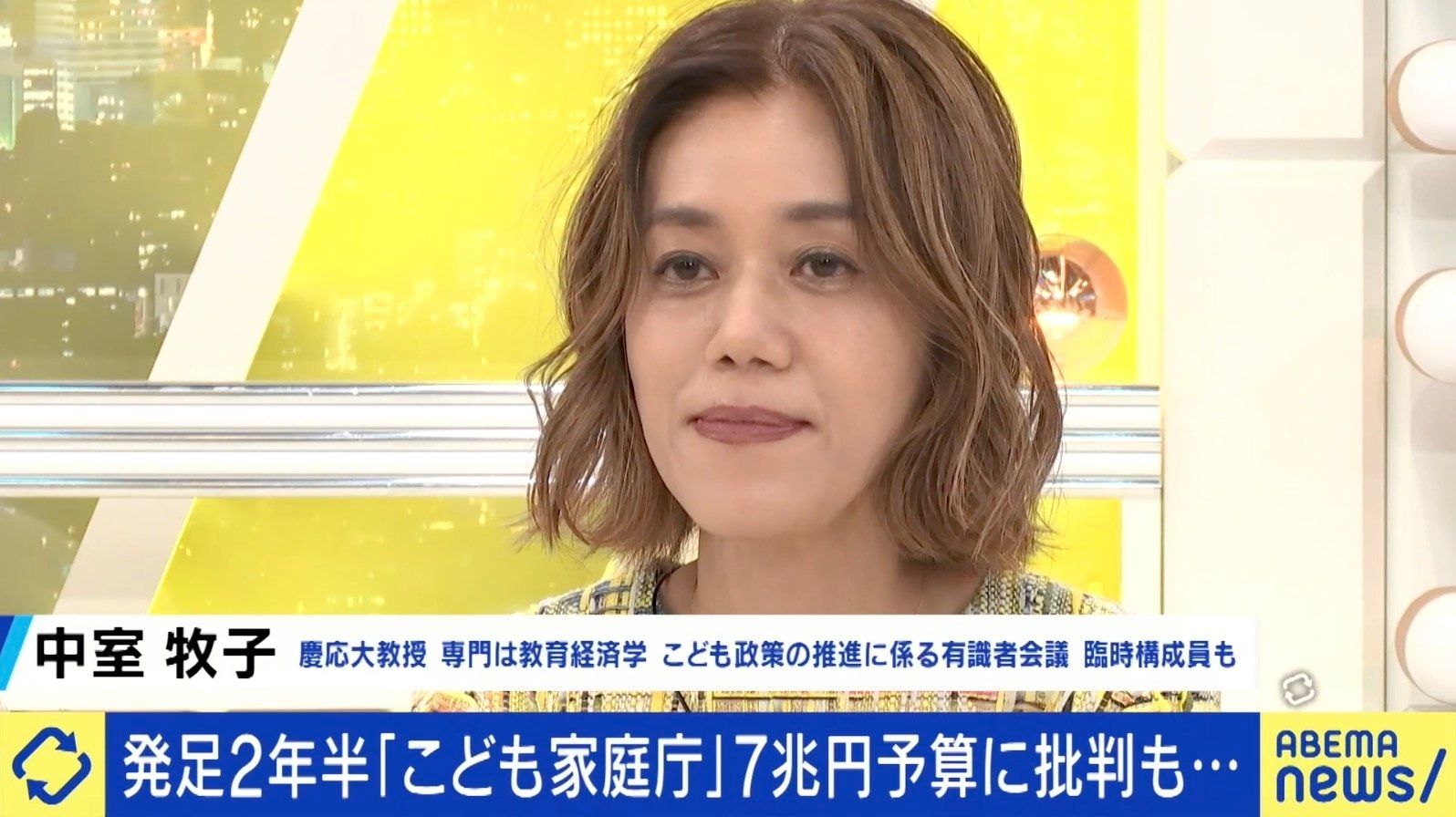
こども家庭庁設立にあたる有識者委員会にも参加した慶応義塾大学の中室牧子教授は、「予算に関する批判は無意味だ」と考えている。2年間の評価として、いじめ、虐待、ヤングケアラー、少子化対策など子どもに関する課題を「一つの窓口に集約」したことや、保育現場の処遇改善(月額3.8万円昇給)などの「子どもに関する職業の待遇改善」、子どもの権利条約で各国が選任機関を整備するなど「国際社会との協調」を挙げる。
存在意義については、「こども家庭庁設立に尽力した、自民党の自見はなこ参院議員は『こども基本法の理念が大事だ』と言っている。子どもを個人として尊重して、人権が保障される状況にしようというのが、こども基本法の理念だ。こども家庭庁は、少子化対策のためでなく、この理念を実行するために作られたが、『少子化対策しかやっていない』と違和感が出ている。原点に立ち返り、もし権限が弱いなら強化して、理念を実行に移すことが大事だ」と語る。
「日本若者協議会」代表理事の室橋祐貴氏は、こども家庭庁の施策にはズレがあると指摘する。「ユニセフの調査では、日本の子どもの“精神的幸福度”が、36カ国中32位だった。“身体的健康”は1位だったが、幸福度としては低い。これはこども家庭庁が、もっと正面を切って取り組む課題だ」。
また、「暴力事件で高校野球を辞退した高校もあったが、そうした場所に、こども家庭庁がどこまでコミットしているか。勧告を出す権限はあっても、なかなか出す機会がない。子どもの意見が反映されていない“ブラック校則”にもコミットできていない。『少子化対策のための省庁』ではなく、子どもの幸福を真ん中に据えて、施策を洗い出す必要がある」と求めた。
■“独身税”と炎上したことも

こども家庭庁をめぐっては、2028年度に医療保険負担額を月々450円/人程度の負担増とすることにより、児童手当、出産時の支援給付など0〜18歳の給付拡充(1人あたり146万円増)を行うとして、“独身税”と炎上した過去もある。Xでは「少子化を止めることができないのに、国民から独身税を取ろうとする」「独身税徴収…結婚は縁なのに独身でいることが悪のよう」といった批判が見られる。
室橋氏は「現役世代の中で、お金を循環することに限界が来ている」との考えを示し、「社会保険料の負担はすでに相当高いが、一部には余裕のある高齢世代もいる。そうした人々にきちんと負担してもらい、こども家庭庁に『日本社会全体で子どもを育てる』という雰囲気を打ち出して欲しい」と願う。
以前こども家庭庁の部会委員を勤めていた大空幸星衆院議員(自民党)は、「現役世代の負担が生じることに対して、あまり正面から向き合ってこなかった。“国民健康保険料”ではなく、“国民健康保険税”として徴収している自治体もある。最初の議論で、これにも触れるべきだった」と話しつつ、「中長期的に見て、許容して欲しいという思いが根底にある」と説明する。
■「中身は変えなくていいから、説明の方法を変えた方がいい」
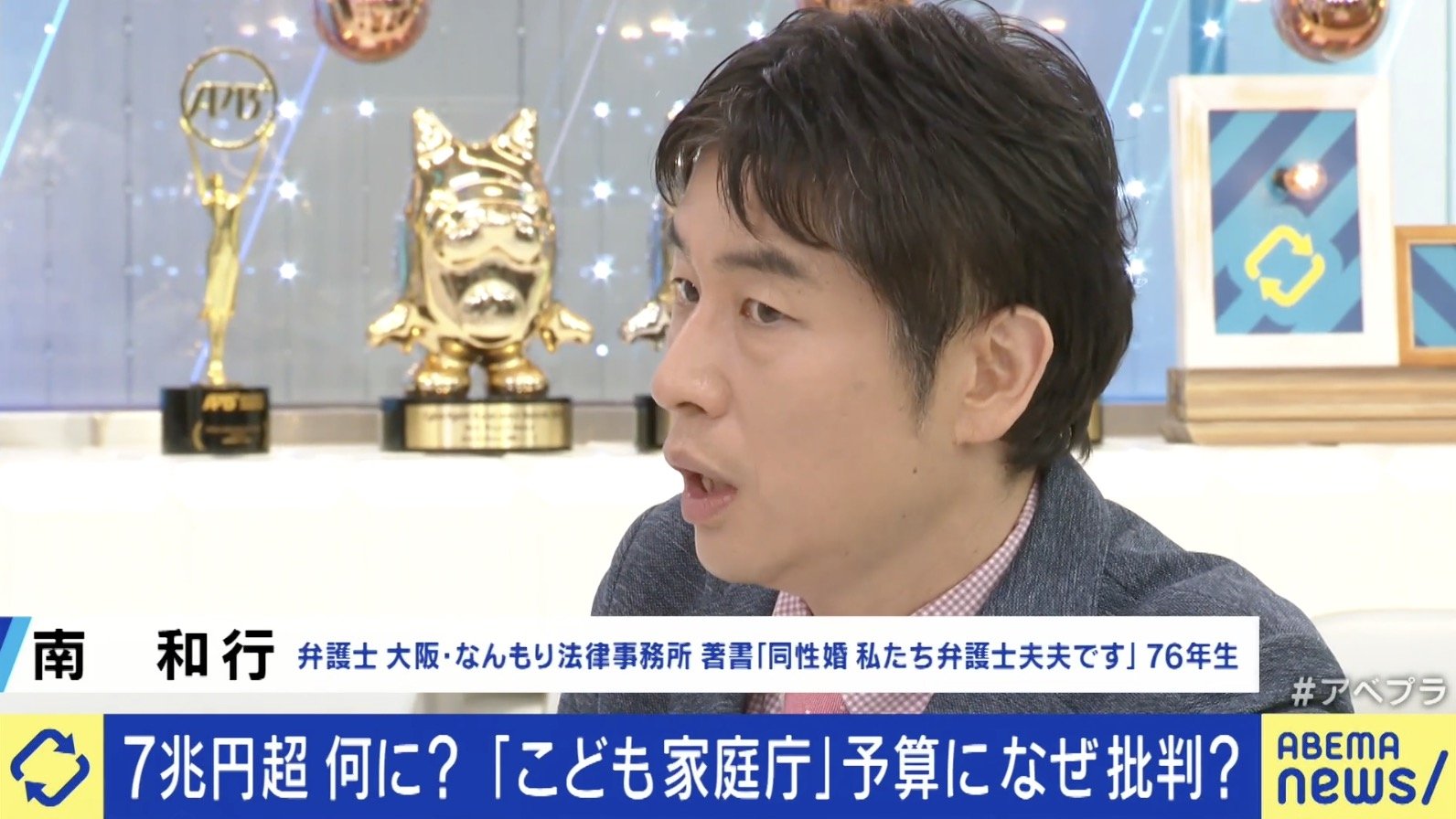
中室氏は「教育や子育てに対する投資は、短い目で見てはいけない。国民の側も辛抱しなければいけない部分が確実にある」と語る。「子ども政策も教育政策も、効果を明確に示さない特徴がある。すると国民の納得は得られず、『7.4兆円の無駄遣い』と言われてしまう。行政は効果を明確に示して、それを見た国民も『将来に対する投資だ』と思わなければいけない」。
「なんもり法律事務所」の南和行弁護士は、「各論としては賛成だが、総論として『未来への投資』と言われると、次の世代を産み育てることのない同性婚の自分からすると、『そんなに言われると……』となる」。
具体例として「夏休みにキャンプに行ける家庭と、行けない家庭があるとき、『行けない家庭の子にお金を出したらいい』と各論を見せられれば、納得して賛同できる。『マズそうな給食を無理やり無料にするぐらいなら、もう少し税金を付けておいしくしてあげた方がいい』となれば賛成だ」と話す。
そして、「現実を説明しにくいからといって、『次世代への投資で、いつか効果が出る』と言うと、子どもがおらず“独身税”を取られる人は、ますます抵抗感を持たざるを得ない。中身は変えなくていいから、説明の方法を変えた方がいい」とアドバイスした。
(『ABEMA Prime』より)