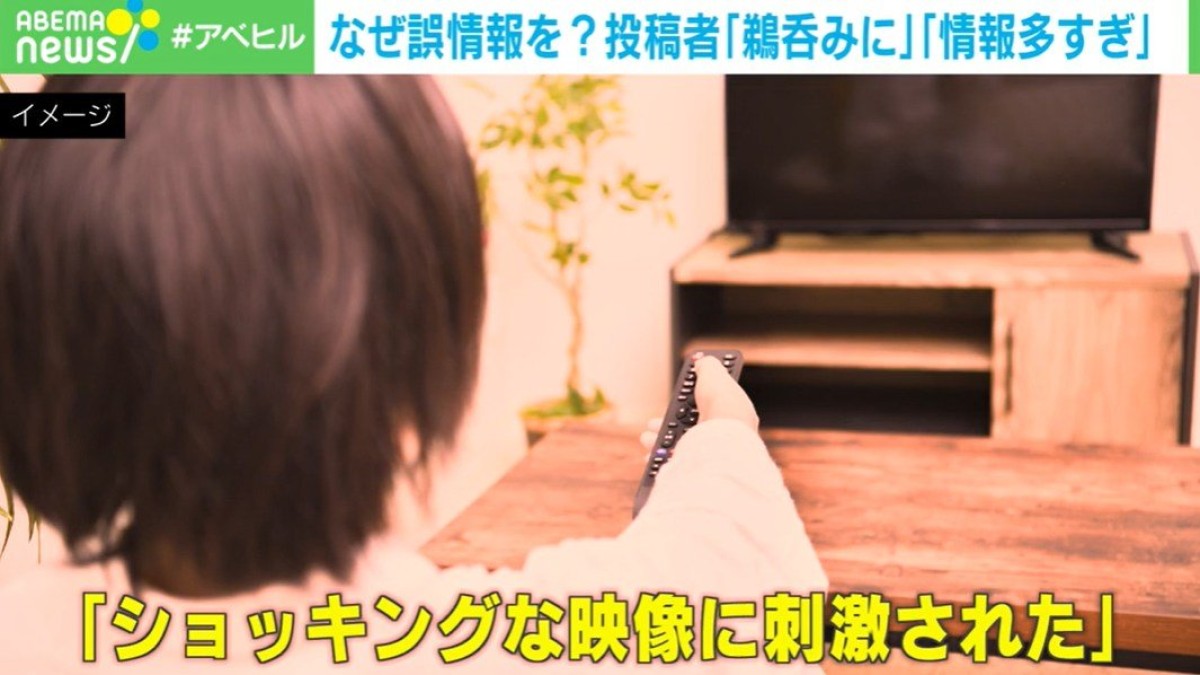7月、日産化学が販売する除草剤『ラウンドアップ』に関して、「ベトナム戦争に使われた枯葉剤と同じ成分」「脳神経発達障害やがんを誘発する」などの誤情報を投稿したとして、投稿者に損害賠償命令が下された。
ラウンドアップと枯葉剤は全く別の成分であり、神経毒性や発がん性については食品安全委員会が「認められなかった」と評価している。(2016年農薬評価書より)
なぜ誤情報の投稿に至ったのか。投稿者が影響を受けたとしているのが「ラウンドアップに毒が含まれている」などと主張するシーンが含まれる映画だ。裁判の過程では、こう述べている。
「映画を見て、その内容を鵜呑みした」「ショッキングな映像に刺激された」(投稿者、以下同)
また、当時の投稿からは、「日本でマスコミ報道されていない」「実態を知って大事な人を守らないといけない」とその内容を信じ、知らない人に伝えるべきと考えている様子がうかがえる。
こうした投稿について、ラウンドアップを製造・販売する日産化学側は削除を要請するも、投稿者は当初、対応しなかった。
「インターネットで改めて調べた際に、情報が100サイト以上と多く、確認するのに時間を要した」
投稿者が確認した情報源としてあげたのは各種の報道記事やまとめサイト。中には疑義が出て取り下げられた論文に基づいた情報などもあった。
農薬等のリスクコミュニケーションに詳しい東京大学名誉教授の唐木英明氏は、以下のように説明する。
「反対派の人たちは非常にわかりやすい物語を作る。我々は健康に『危険だ』という情報の方を信じる。『安全だ』という情報は『本当かな』と思うところがある。だまされてしまうのは、人間の本能として仕方がないところがある」(東京大学名誉教授・唐木英明氏、以下同)
投稿者は最終的には誤情報を認めて謝罪するが、削除するまでに2カ月を要している。
では“情報リテラシー”としてよく指摘されるように、一次情報を確認すればすぐに解決していたのだろうか。
「一次情報」は難しすぎる?
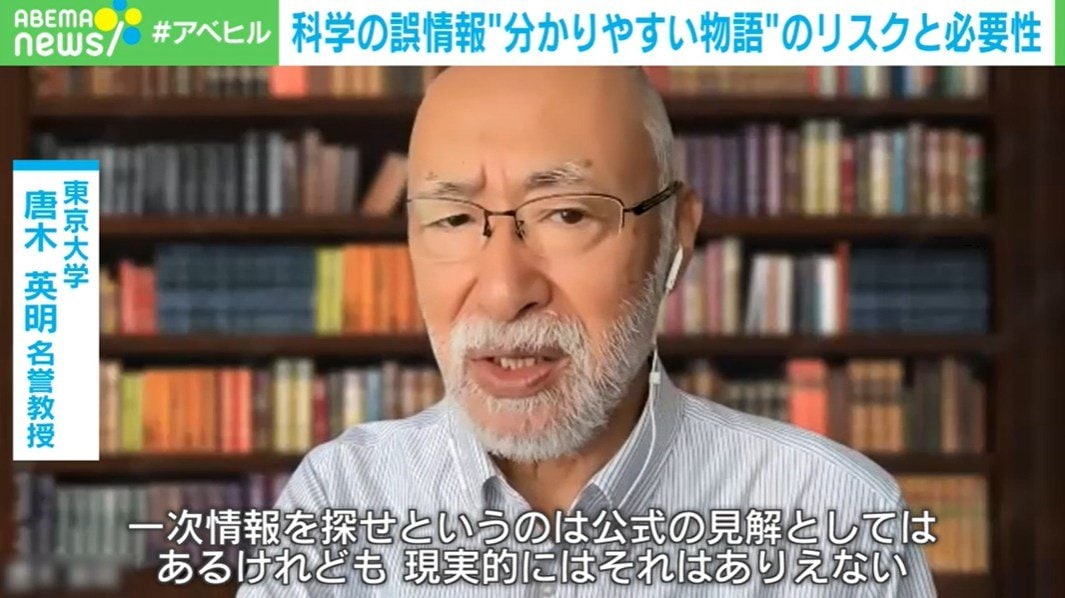
「ほとんど不可能だと思う。我々が読んでも頭が痛くなるような論文だから、一般の人が見て理解ができるとはとても思えない。一次情報を探せというのは公式の見解としてはあるが、現実的にはありえない。そのため、日本では食品安全委員会や厚生労働省などの公的な機関の公的な発表をまず信じてほしい、探してほしいと私はお願いをしている」(東京大学名誉教授・唐木英明氏、以下同)
「しかし公的機関のホームページはこれもまたわかりにくい。科学的に正しいことを書こうとすると、一般の人の心に響かない」
たとえば、投稿者もあげていた「国際がん研究機関(=IARC)が、ラウンドアップの主成分グリホサートを『おそらくヒトに対して発がん性がある』と分類した」という情報。これだけだと「国際機関ががんになると認めた」と思えるが、このIARCの発がん性の分類について、農水省は「正しく理解されていない現状があった」として解説ページを設けている。
この分類は「物質そのものに発がん性があるかどうかの証拠の強さ」であり、発がん性の強さや摂取する量は考慮しておらず、人間にとっての発がんのリスクの大きさを示しているわけではない、ということだ。
食品安全委員会やEUの関連機関などは、その後、発がん性は認められないと評価している。 公的機関のサイトをたどれば、こうした情報を集めることはできるが…。 「『IARCが発がん性があると言い、食品安全委員会はないと言っている』。これは一般の人にはとても理解が難しく、わかりやすい物語が必要だ」
「我々の説明もわかりやすい物語で説明することが大事だと思うが、科学は必ず不確実性があるため『100%こうだ』と断定すると、『お前バカじゃないか』ということになる。したがって『このくらいの確率でこれは正しい』と非常にあいまいな言い方しかできないのが科学の世界。ただ、それでは一般の人には理解されず、『これは安全ですか』と問われたら『安全です』と断定しなければ納得してもらえない」
科学的に正確な情報は、味気なく複雑で人々に届きづらい。一方で、わかりやすさのために物事を断定すると、科学的に不正確になってしまうこともある。そうしたジレンマとの戦いだと唐木氏は語る。
「そのギャップをどう解決するかいつも悩むところだ。科学者や研究者はなかなかそのバリアを越えられないところがあるが、その壁を乗り越えて物語を作らないと、相手には勝てない。その点を我々も十分考えてリスクコミュニケーションを行い、科学の物語を語っていく覚悟が必要だろう」
(『ABEMAヒルズ』より)