「怖くて病院に行けない」「すべての医療で性別情報が必要なのか?」。Xでそんな声を上げたのは、トランスジェンダーの人々。認定NPO法人ReBitの調査によると、トランスジェンダー男性と女性で、「医療での困難を経験した」と答えた人は77.8%だった。
【映像】「喉を痛めると男性的な声に」 トランスジェンダー(MtF)のマキさん
ネットの声を見ると、問診票などで性別を記載しなければいけないこと、ホルモン投与をしていると申告したことで物珍しげな顔をされるなど、理由はさまざま。病気やケガを直すためとはいえ、性別に触れられることに苦痛を感じてしまうようだ。
一方で、「医療に必要なのは肉体が女か男かでしょ」「男女でかかりやすい病気も違うんだしそこは割り切ってほしい」といった厳しい意見も。
『ABEMA Prime』では当事者を交え、病院への行きづらさと、医療現場の事情を考えた。
■「喉を痛めると男性的な声に」「診察室にやたら大勢の看護師が」 当事者の苦悩
ライフネット生命の調査(2023年)によると、男性として生まれ性自認が女性(MtF:Male to Female)の33.8%、女性として生まれ性自認が男性(FtM:Female to Male)の43.7%が、「体調不良でも医療機関に行くことを我慢した経験がある」と答えている。
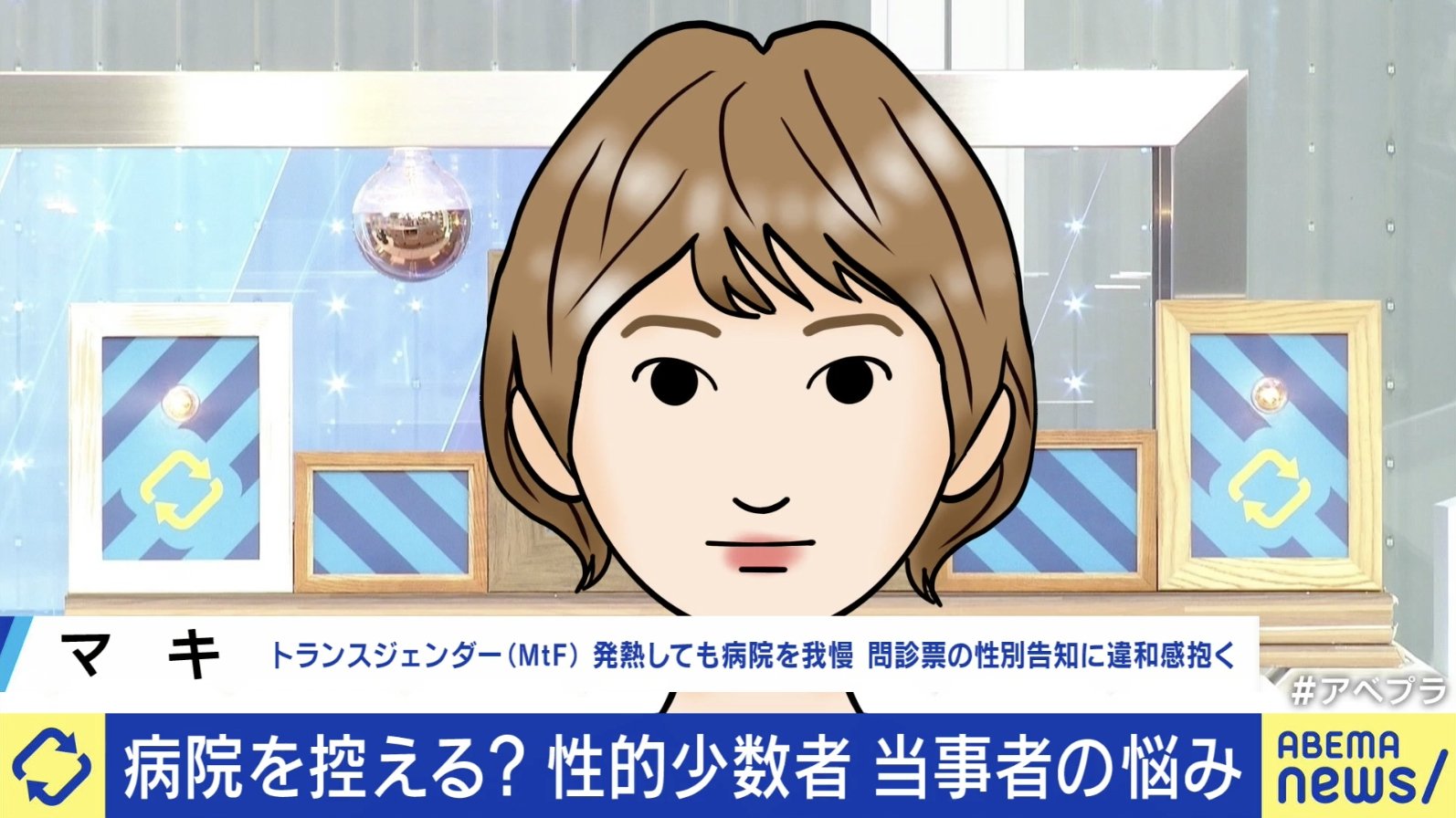
MtFのマキさんは、健康診断の際にフルネームで呼ばれ、男性的な名前が現在の容姿となじまないために、周囲が一瞬「えっ?」という空気になった経験がある。普段は女性的な声質だが、喉を痛めると男性的な太い声になってしまうため、風邪などを引いても病院の受診は控えるという。「誰からも男性として認識されたくない。例えば待合室にご近所さんがいて、噂話をされてしまったら、日常生活にどんな悪影響が及ぶかわからない」。
また、入院した知人の例として、「院内で着る服や入浴できる日が、性別で分けられていると。入院すると、容姿を女性として認知されるように保つ、いわゆる“パス”する状況を保つのがすごく難しい」と説明。さらに、周囲から攻撃的な目を向けられやすい風潮があることを訴えた。
FtMの田中さんは、病院では戸籍性を名乗ると割り切っているという。しかし先日、猫にかまれて初診の外科を受診した際、診察室にやたら大勢の看護師がいると感じると、問診票の既往歴に記載した「性別違和」の箇所がペンで強調されていたそうだ。「おそらく、物珍しいから看護師の方が見たかったのかな、そういう扱いをされてしまうんだなとがっかりした」。
■アレン様「“悟って”は無理。本人たちから意思を伝えるのが大事」
一般社団法人にじいろドクターズ代表理事の坂井雄貴氏は、保険診療では制度上男女の登録が必要で、診療上でも性別情報は大事だと説明する。それは、どんな臓器(生殖器や子宮)を持つか、生理、ホルモンの状態などは重要で、同じ症状でも男女によって想定すべき病気・状態が変わるため。一方で、問診票等への記入が必要かは別問題だと指摘する。
「保険証の性別がそのままシステムに反映されるので、それをわかった上で、“多分こういう状態だろう”と推測して診察が始まる。ただ、トランスジェンダーの方は特に、体の状態や治療の有無・状態が個人で大きく違う。そこで勝手な思い込みが生まれると、診断や治療を誤ることに繋がってしまうので、そこはまず医療者が知っておかなければならない。また、『自分の体の状態はこうです』と安心して話せる環境がないと、信頼してもらえない。どうすれば双方がうまく情報を伝えられるかはすごく大事だ」

“大物マダムタレント”のアレン様は、「キツイ言い方かもしれないけど、本人たちからある程度意思を伝えるのが大事だと思う」との考えを示す。「大病を患ったり、一刻を争う状態の時に、『病院に行きたくない』とか性別とか言ってられない。私も本名を呼ばれたくないから、かかりつけの病院ではドクターや受付の人に『私の時は名前呼ばないで』って伝えてて、私の時だけ呼びに来てくれる。『こういう性別の者で、自分をこう自認してます。少し配慮いただけるとうれしいです』ってひとこと言えば、まるっきり変わるかはわからないけど、先生や周りの人の頭には入る。それだけでも違うと思う。大多数の人を処置している医療従事者に“悟ってください。わかるでしょう”は正直無理だと思うから、やっぱり自分からある程度アクションを起こさないと」と話した。
田中さんは「我々が望んでいるのは特別扱いではなくて、つつがなく診察が終わること。ただそれだけ」としつつ、「私は男性自認のセクシュアリティだが、男女どっちともつかない自認であるとか、あえて決めていない、もしくは決められていない状況の時に、“こう扱ってください”と伝えるのはすごく難しいと思う。さらに言えば、『体は女性です』と割り切って伝えたつもりであっても、向こうからは『社会的に女性です。そう扱って大丈夫です』と誤解されることもある。生物学的な性別と、社会生活の性別、表現したい性別は必ずしも一致しないが、その前提自体が相手に共有されていない」と問題提起した。
■小原ブラス氏「今は自分にちょうど良い病院を見つけた」
ゲイを公表しているコラムニストの小原ブラス氏は、「今回はLGBTQ、トランスジェンダーの話だが、他のマイノリティの方もいっぱいいる。僕は女性に裸を見られたくないから、健康診断の時は『年上の看護師の方いますか?』と聞いて、現場で嫌がられて断られたりする。ダメだったら次は違う病院にして、今は自分にちょうど良い所を見つけた。いろんな性やマイノリティがあるからこそ、ガチガチに決めるのではなく、やはりコミュニケーションなんだと思う」との考えを示す。
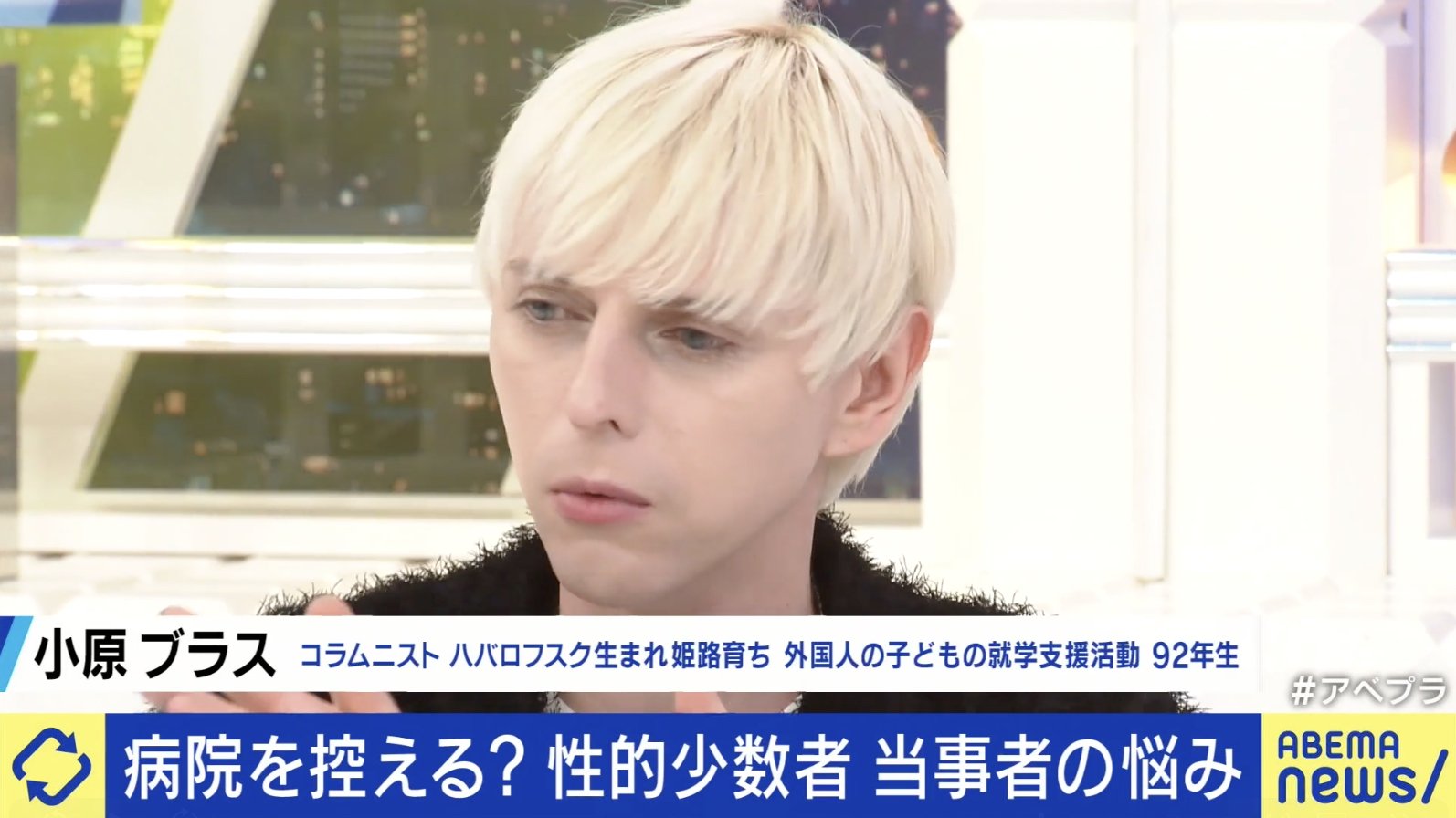
一方、音楽プロデューサーの松尾潔氏は、「それができるのは、言える強さがある人だけかもしれない。そうではない人にも寄り添うようなシステム作りは、同時に進めていくべきだと思う。ストレスを1人でも小さくしようと思ったら、厚労省レベルでの教育が必要な段階に来ているのでは」とコメント。
坂井氏は、「いろんな性的少数者の方がいて、トランスジェンダーも本当に多様だ。私たちは個人情報を取り扱い、困った時には見る必要がある。教育の機会がないために、そもそも認識すらできていない状態だと、配慮のしようもないので、学んでいかなければいけない」とした。(『ABEMA Prime』より)
