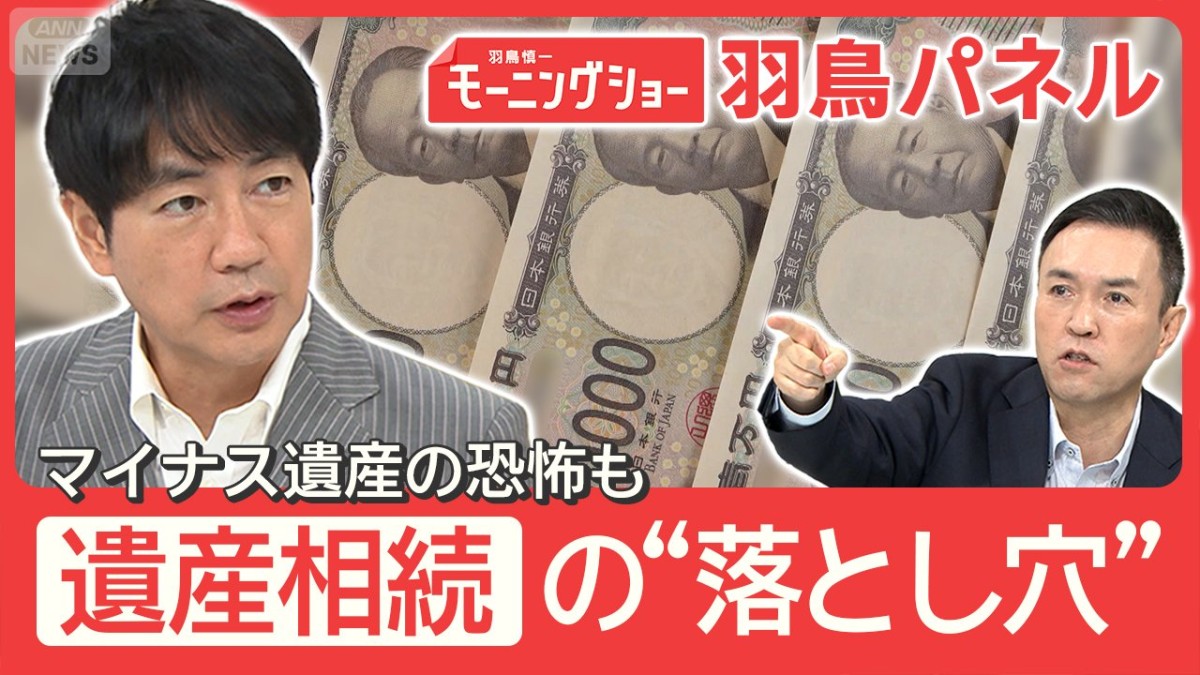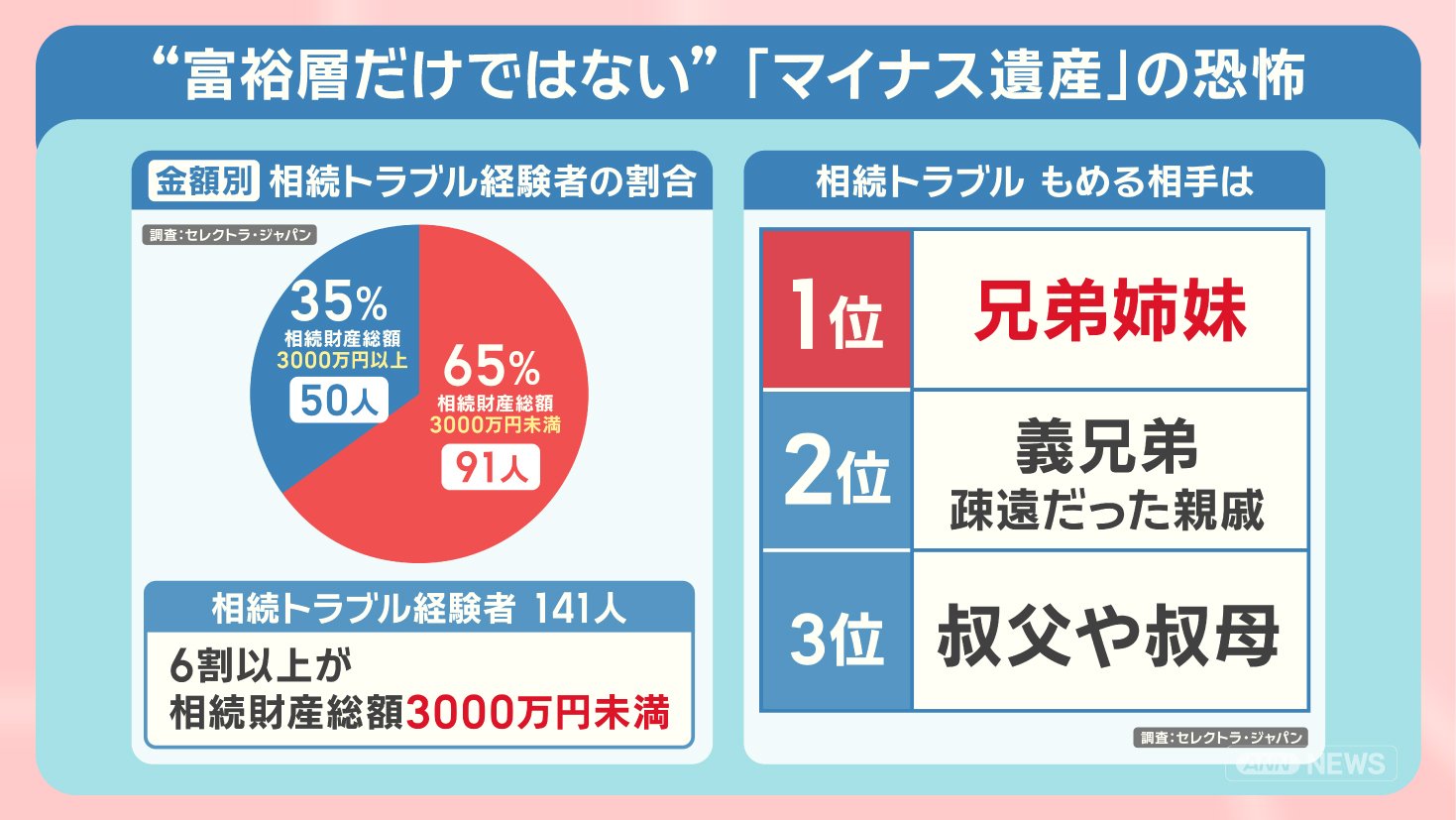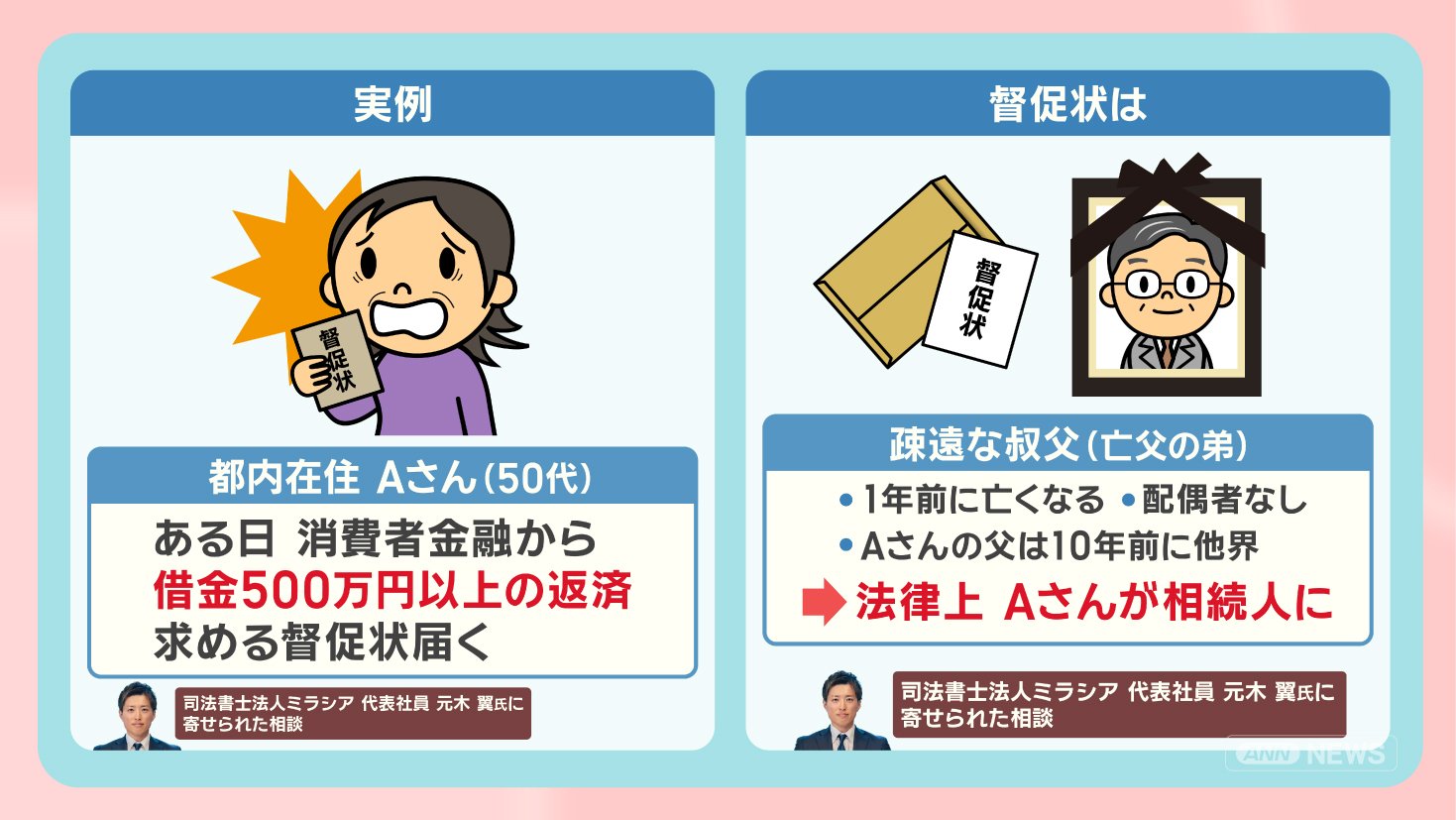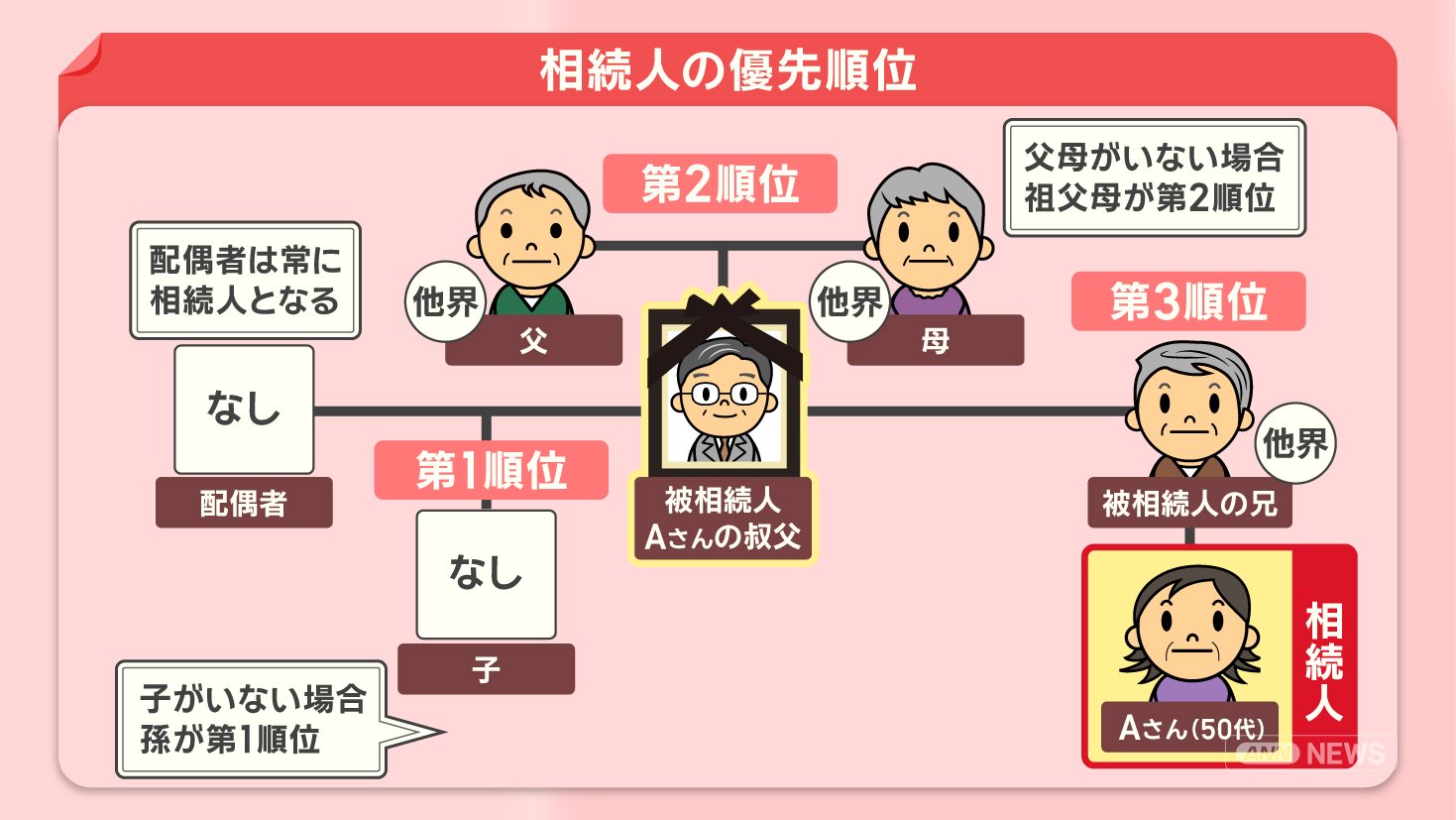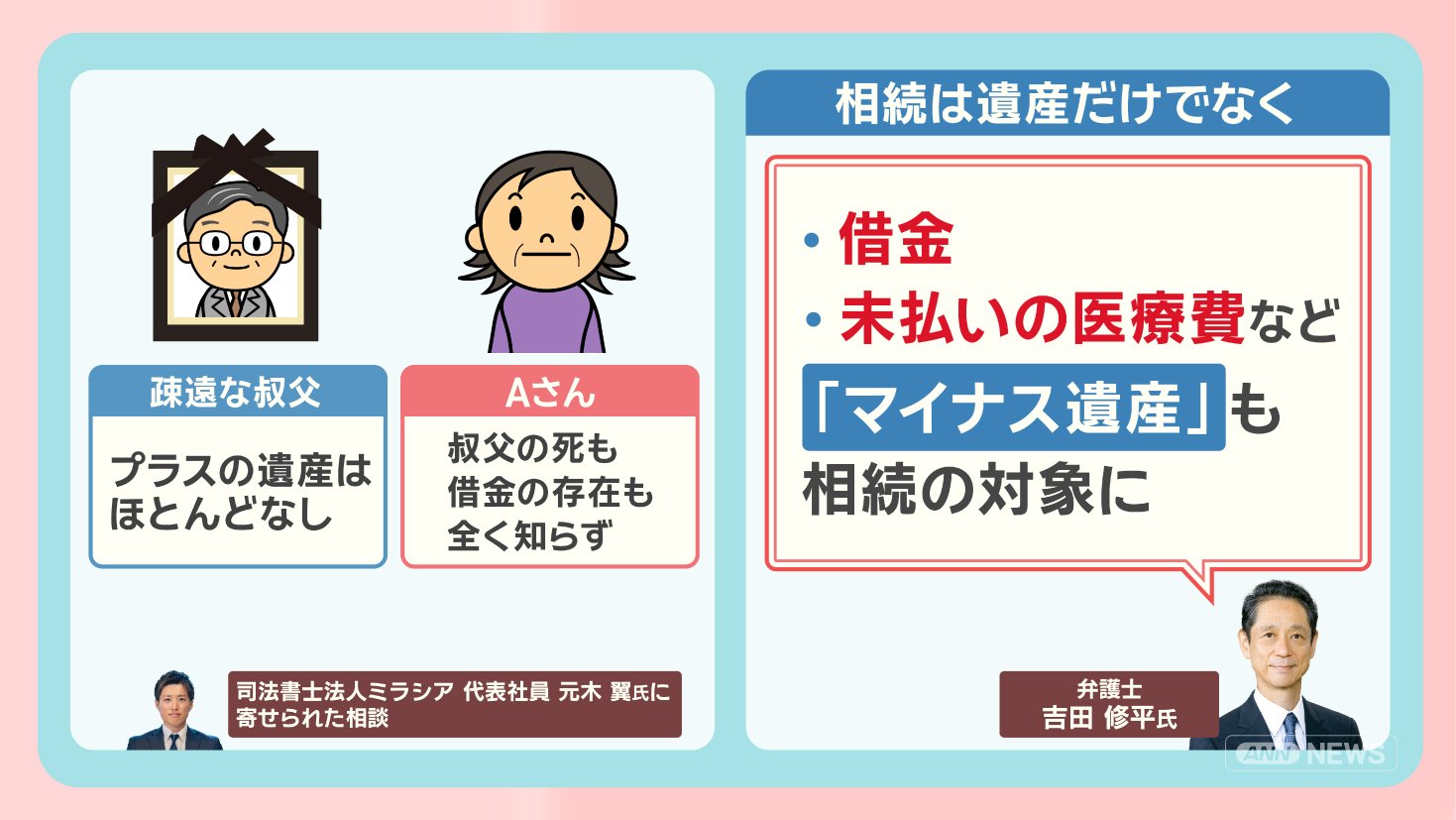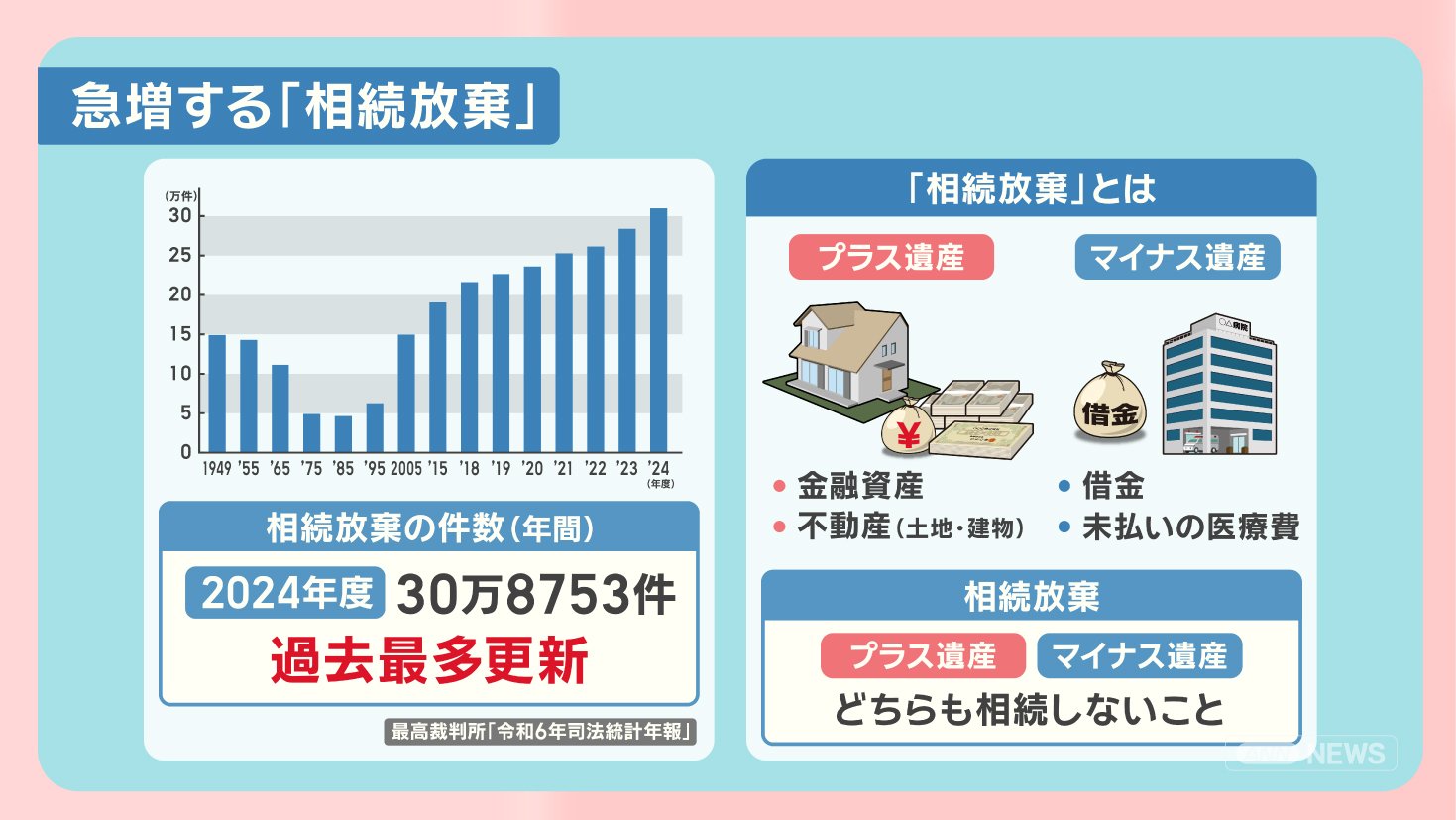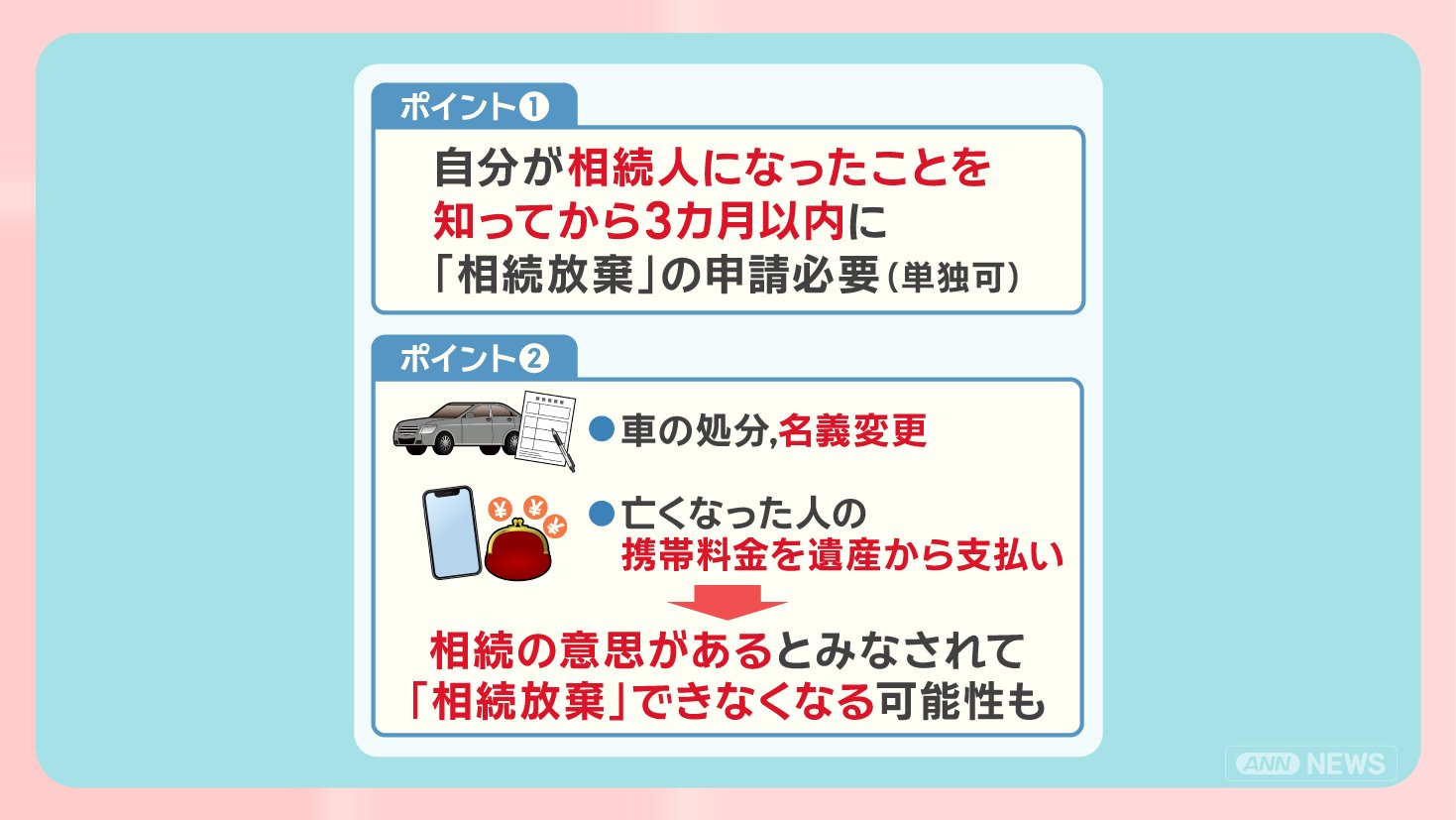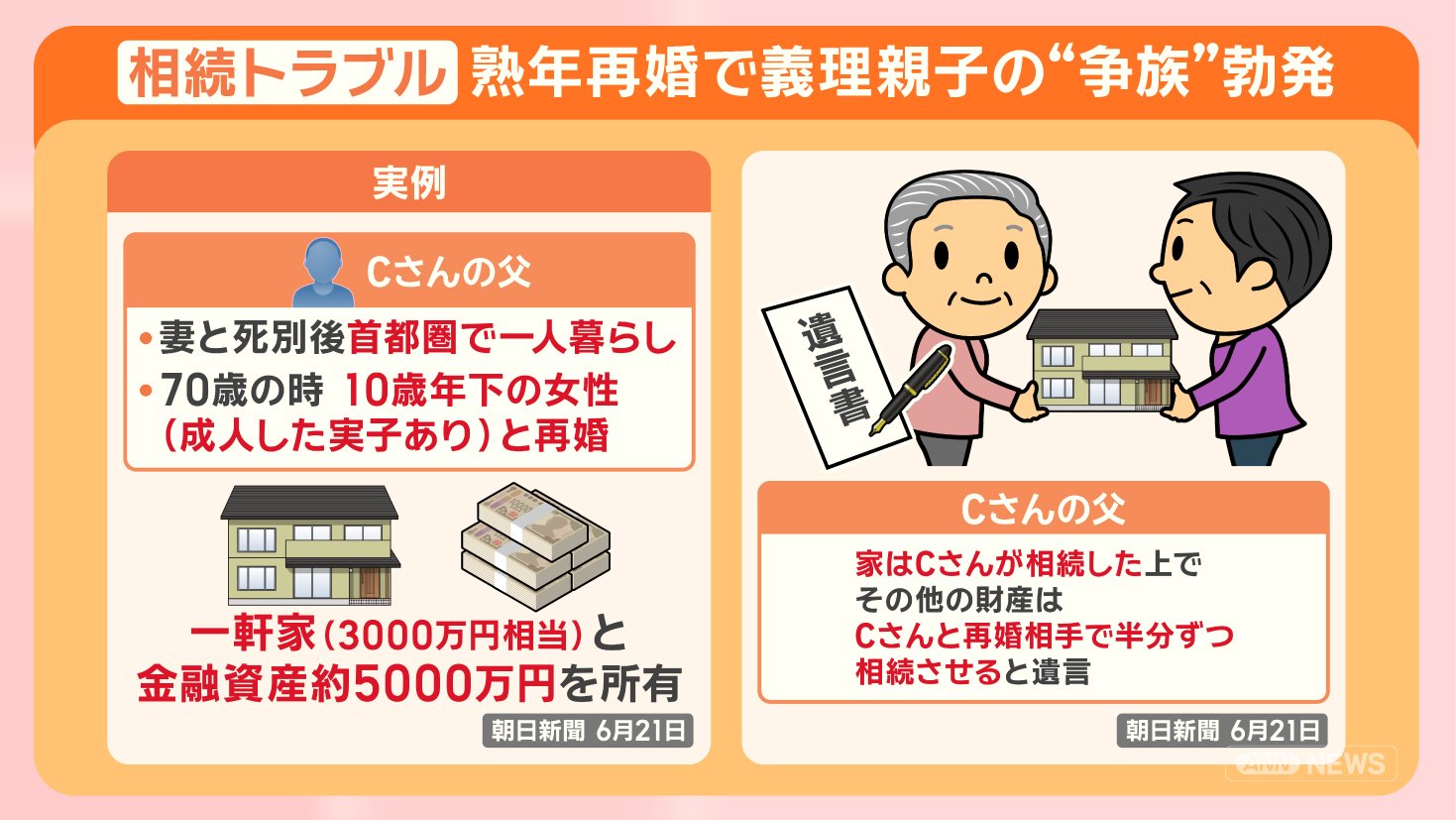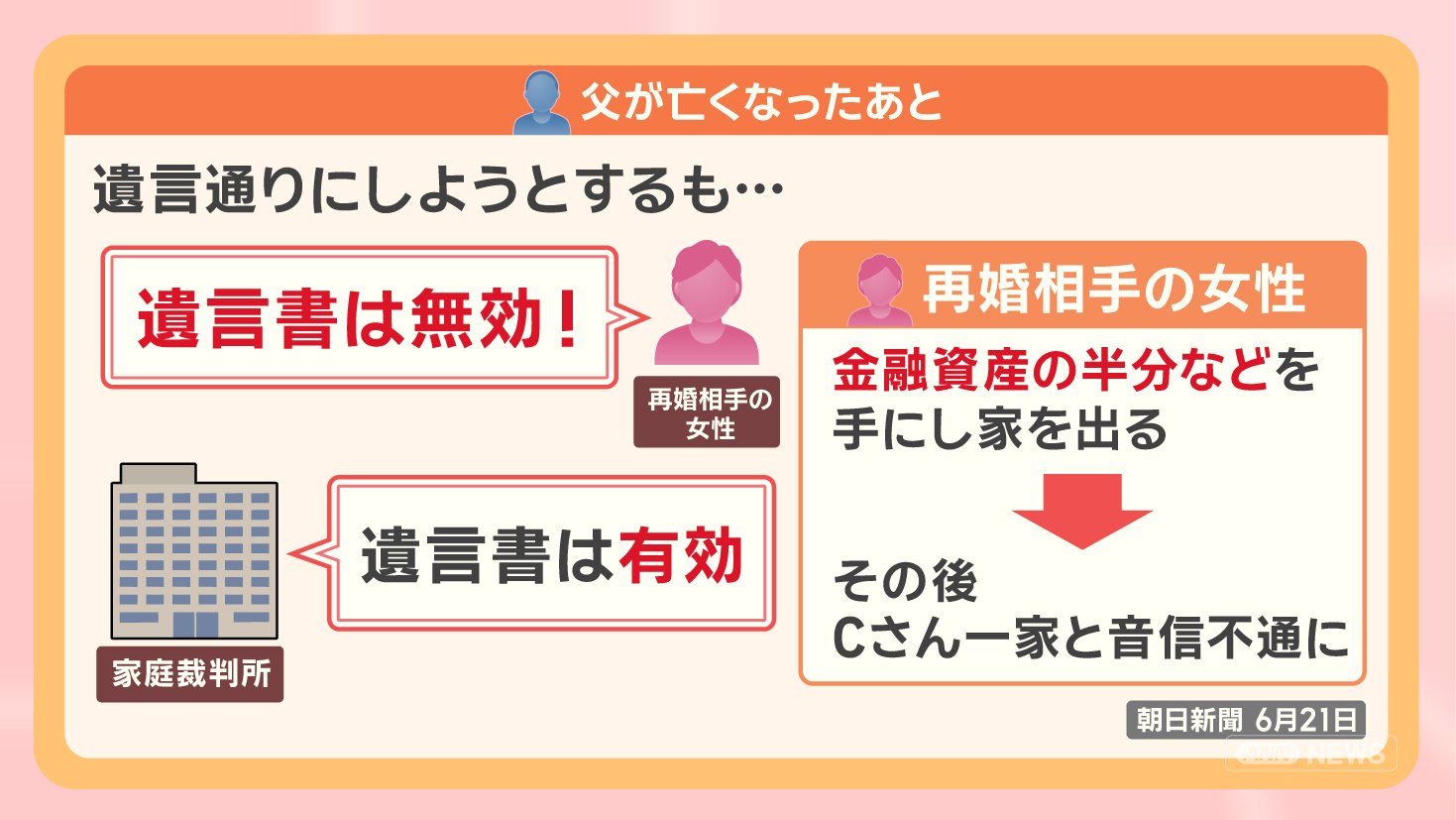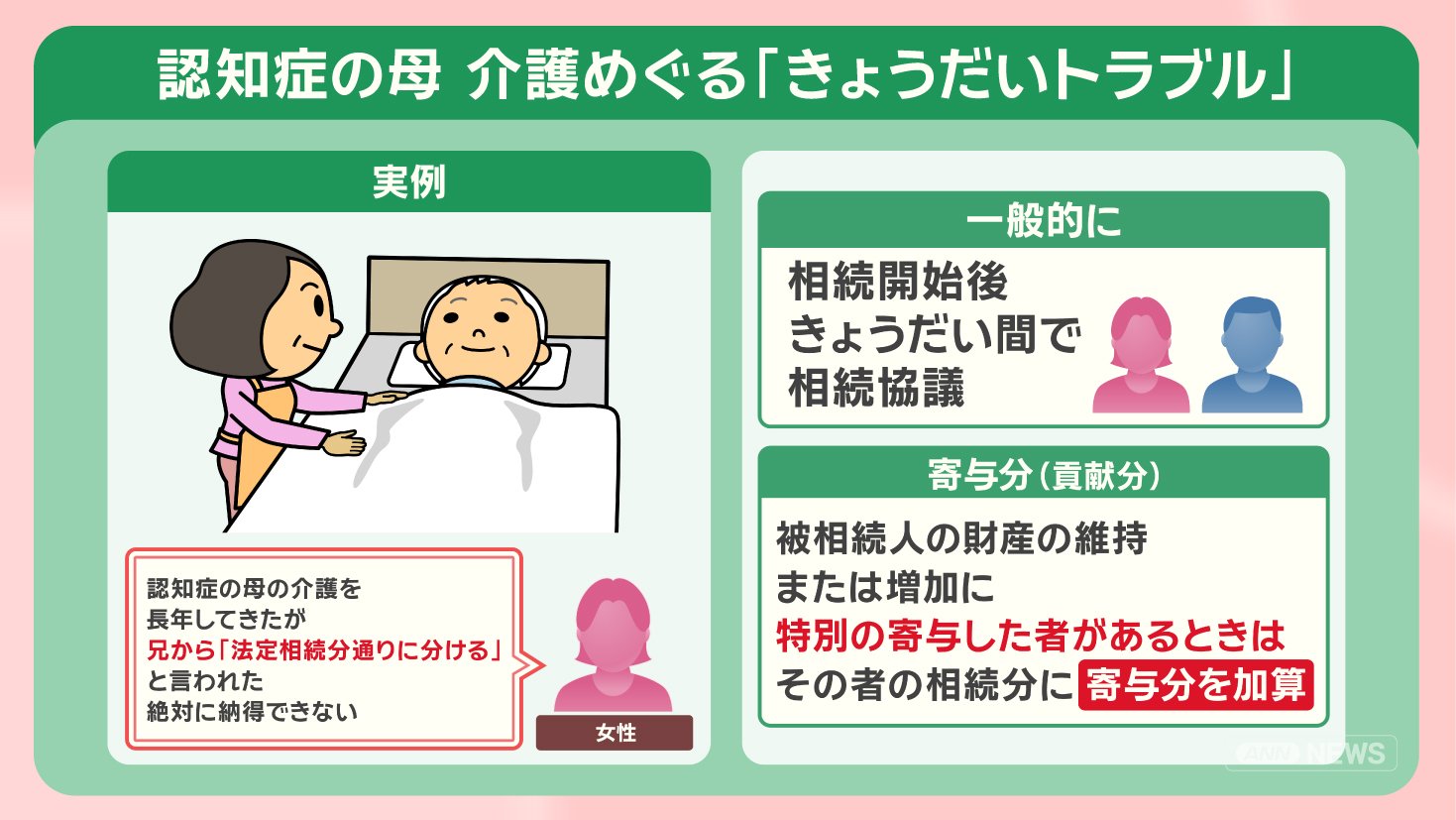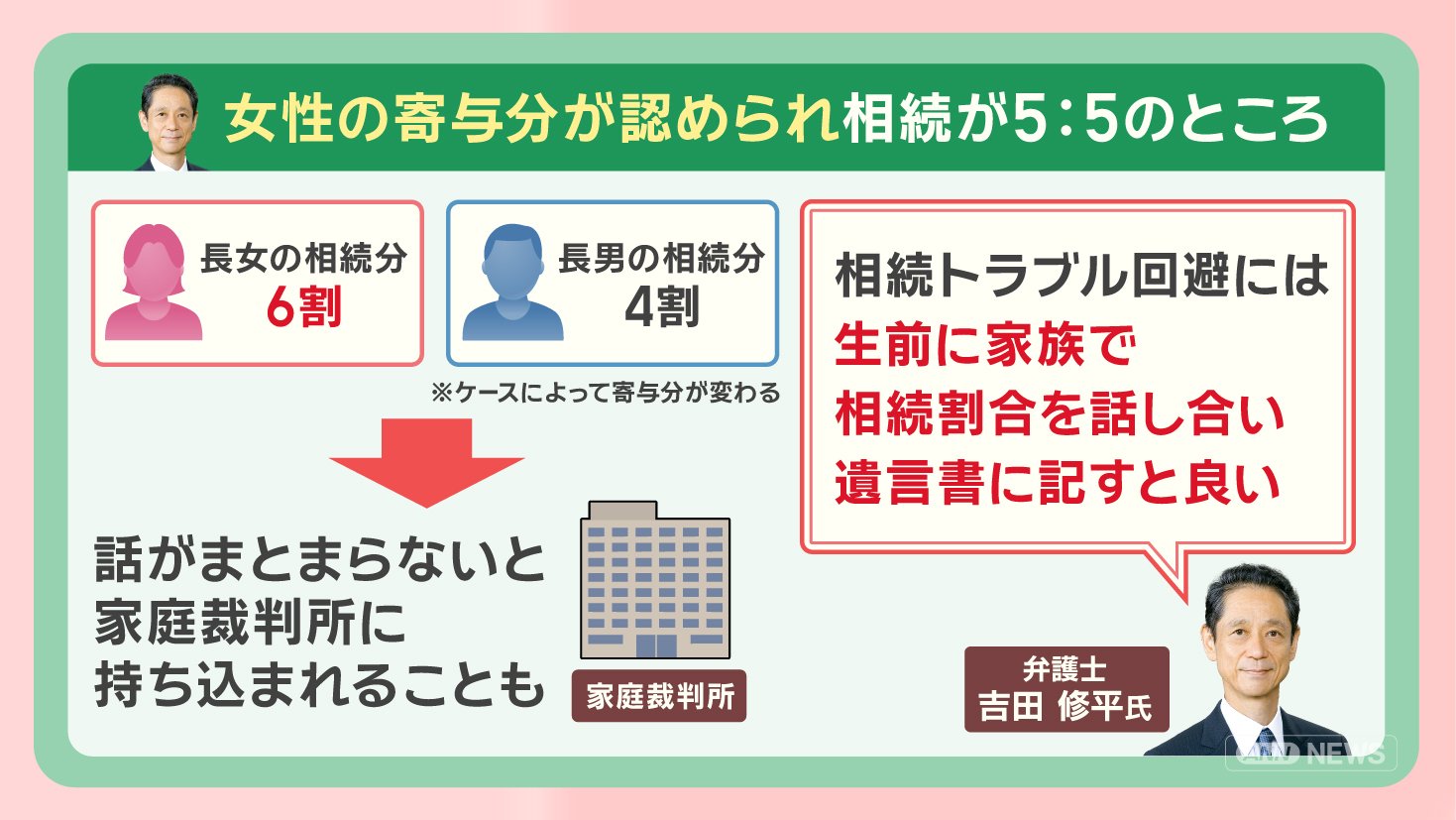金額の少ない相続のトラブルが増えています。
中には、疎遠な親戚の借金が、相続として突然降りかかってくるケースもあります。
家族でもめる前に知っておきたい、相続について見ていきます。
■『電子マネー』『ポイント』『マイル』相続できる?
皆さんが持っているスマホの中にある資産、相続できるのでしょうか。
『電子マネー』は、相続できます。
一部例外もありますが、一般的には相続が可能です。
『ポイントカード』は、基本的には相続できません。
一般的に、本人のみが使用することが想定されています。
(※中には、相続できるものもあります)
『日本の航空会社のマイレージ』は、相続できます。
ANA(全日空)もJAL(日本航空)も、マイルは相続財産になります。
■相続で争う金額や相手は?疎遠な親戚の借金500万円が…
相続の問題は、富裕層だけに関係があるわけではありません。
金額別の相続トラブル経験者の割合です。
6割以上が、相続税の対象とならない、相続財産総額3000万円未満です。
相続トラブルでもめる相手は、
1位が、『兄弟姉妹』です。
2位は、『義兄弟』や『疎遠だった親戚』、
3位は、『叔父や叔母』です。
こういうケースがありました。
都内在住のAさんに、ある日、消費者金融から、借金500万円以上の返済を求める督促状が届きました。
この督促状は、疎遠な叔父のものでした。
Aさんの叔父は、1年前に亡くなり、配偶者はいません。
Aさんの父は、10年前に他界していて、法律上、Aさんが相続人となります。
相続人の優先順位を、Aさんのケースで見ていきます。
Aさんの叔父である被相続人には、相続人となる配偶者がいません。
さらに、相続の優先順位が1位となる、子や孫もいませんでした。
そうなると、2番目は、被相続人の父・母ですが、すでに他界しています。
3番目に回ってくるのは、被相続人の兄(Aさんの父)です。
しかし、この兄も他界していたため、姪のAさんが相続人となりました。
疎遠な叔父は、プラスの遺産はほとんどなし。
Aさんは、叔父の死も借金の存在も全く知りませんでした。
「相続は、(プラスの)遺産だけでなく、借金や未払いの医療費など『マイナス遺産』も相続の対象になる」ということです。
このマイナス遺産に関連して、近年、『相続放棄』の件数が増えています。
2024年度は、30万8753件と過去最多を更新しています。
この『相続放棄』は、『金融資産』や土地・建物といった『不動産』のような『プラス遺産』、『借金』『未払いの医療費』といった『マイナス遺産』、このどちらも相続しないことです。
『相続放棄』で注意するポイントです。
1つ目は、自分が相続人になったことを知ってから、3カ月以内に、『相続放棄』の申請が必要です。
相続人が複数いた場合でも、単独(個人)で申請することができます。
2つ目は、
1、車の処分・名義変更、
2、亡くなった人の携帯料金を遺産から支払う、
このような行為をしてしまうと、相続の意思があるとみなされて、『相続放棄』ができなくなる可能性があります。
■熟年再婚で相続トラブル 義理親子で争いも
そして、こんなケースも。
Cさんの父は、妻と死別後、首都圏で一人暮らし。
70歳の時に、10歳年下の女性(成人した実子あり)と再婚します。
父には3000万円相当の一軒家と、金融資産約5000万円がありました。
Cさんの父は、生前、家はCさんが相続した上で、その他の財産は、Cさんと再婚相手で半分ずつ相続させると遺言を残します。
Cさんの父が亡くなったあと、Cさんは、遺言通りにしようとしましたが、再婚相手の女性が、「遺言書は無効」と主張。
しかし、裁判所は「遺言書は有効」と認めました。
再婚相手の女性は、金融資産の半分などを手にして家を出ました。
その後、Cさん一家と音信不通になりました。
■介護めぐる『きょうだいトラブル』相続割合どうなる?
そして、『きょうだいトラブル』のケースです。
「日常生活もままならない、認知症の母の介護を長年してきたが、兄から『遺産は法定相続分通りに分ける』と言われた。絶対に納得できない」と主張します。
一般的に、相続開始後、きょうだい間で相続を協議しますが、寄与分(貢献分)という制度があり、
『被相続人の財産の維持または増加に、特別の寄与した者があるときは、その者の相続分に寄与分を加算』される場合があります。
吉田弁護士が担当したケースでは、女性の寄与分が認められ、それぞれ相続が5:5となるところ、長女の相続分は6割、長男の相続分は4割となりました。
なお、ケースによって、寄与分は変わってきます。
話がまとまらないと、家庭裁判所に持ち込まれることもあります。
「相続トラブル回避には、生前に家族で相続割合を話し合い、遺言書に記すと良い」ということです。
(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年10月3日放送分より)