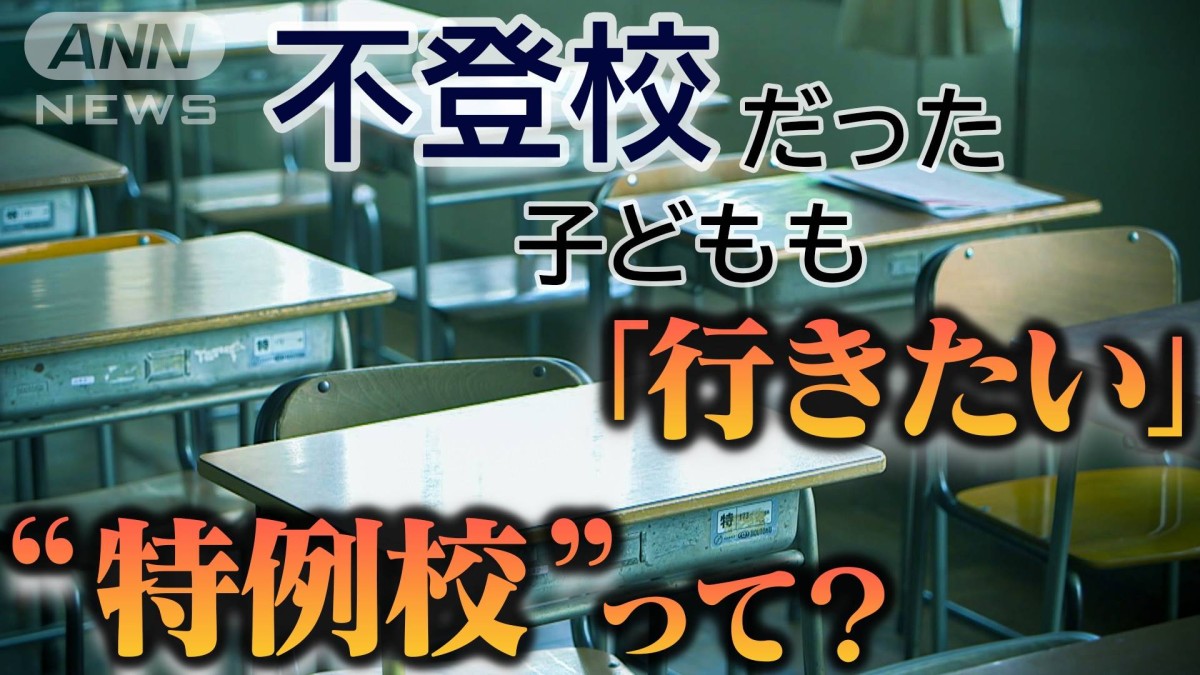【中学生20人に1人が不登校 学校に行けない子どもも通える“特例校”って?】
「たくさんの人に合わせるのが苦手」、「学校の雰囲気が落ち着かない」、「朝、起きられなくなった」…。様々な理由を抱え、学校に行けない「不登校」の子どもたちが増え続けている。
文部科学省によると、2021年度、学校を30日以上欠席した不登校の小中学生は、24万4000人を超えた。9年連続で増え続け、過去最多となった。中学生では、20人に1人の割合だ。
子どもたちを苦しめているものとは?また、学校にはどんな課題があるのか?
不登校の子どもが増え続ける中、「行けない」と言っていた子どもたちが、休まずに登校する学校がある。「学校らしくない学校」とはどんな場所なのか?
■ 「集団になじめない」と気づいた子どもたち
中学3年の女子生徒(14)は、1年ほど前から学校に行けなくなった。幼稚園のころから、なんとなく集団生活に違和感があった。小学生になると、友達の輪に入ることができないこともあり、学校を休みがちになった。はっきりとした理由やきっかけはないが、女子生徒は「幼いころから、周りの人に合わせるのが苦手だった」と振り返る。
女子生徒は、4月から福島県会津若松市のフリースクール「寺子屋方丈舎」に通っている。毎日来なくてもいいし、テストもない。そんな気軽さを感じ通い始めた。ここには同じような思いを抱えた子どもたちが通っている。
朝、起きられなくなったという子もいれば、毎日決められた時間に行くことが苦しかったという子もいた。学校に行けなくなった状況は様々だが、その理由や原因がはっきりとしているという子どもは少なかった。
寺子屋方丈舎の理事長・江川和弥さん(フリースクール全国ネットワーク代表理事)は、「子どもたちが学校に行けない理由は、とても複雑です。学校だけじゃなく、たくさんの要素に悩んでいることもある。自分で説明できない何かがあるのだろうし、うまく説明が出来たら子どもたちも苦しまなくて済む」と話す。
江川さんは、集団を避けてきたコロナ禍を経て、学校に違和感を持つ子どもたちが増えてきていると感じている。
「学校に行けない子どもたちの多くは、個人よりも大勢を優先するということに違和感を持つのかなと感じています。集団がリスクになった時期を経て、理由は様々ですが、『集団になじめない』ということに気がついた子どもが多いと感じています」。
■ 学校が「今の社会とかけ離れた場所になった」
寺子屋方丈舎には、10歳〜19歳までの子どもたち20人が通っている。子どもたちは誰かに合わせることなく、自分のペースで一日を過ごす。
4月から通い始めた女子生徒もほぼ毎日ここに通い、勉強をしたり、絵を描いたりしている。「何を描いているの?かわいいね」。スタッフの女性や友達が声をかけてくれることで、自然と会話が生まれていく。女子生徒はそんな時間が楽しいという。「家にいても苦しかったけど、ここに来てすごく気持ちが楽になった」と話した。
「学校に合わないことを問題視するよりも、子どもたちがダメージを持たないということが大事」として、江川さんたちスタッフは子どもに寄り添っている。
「少子化にもかかわらず、これだけ多くの子どもたちが学校に行かないという選択をしているということを、大人たちはちゃんと受け止めなきゃいけないと思うんです」。
長年、不登校の子どもたちを見てきた江川さんは、学校という場所が、今の社会とかけ離れた場所になってきていると感じている。
「今は多様性を認める世の中になってきている。一方で、学校という公教育の中は選択肢が少なく、合わせる文化が残ってしまっている。そこが一番息苦しく感じるところなのかなと思います」。
江川さんは、学校に行けない子どもたちが必要な教育を受けられるよう、学校以外の学びの場を増やすことに加え、学校の環境そのものを変えていくことが必要だと感じている。
「学校を多様化するためには、学校に行けないという子たちを、どう学校の中に取り入れていくかということだと思います。必要な学びを子どもたちが手に入れることができるよう、官民が力を合わせていかないと、と感じています」。
■ 先生たちも苦悩…学校を変えるには?
国も対策を進めている。今年3月には「学びにアクセスできない子どもたちをゼロにする」として、子どもたちが学べる場所を学校の内外に整備するなどの対策を打ち出している。
その中の一つが「学校の風土の見える化」だ。文科省は「学校の風土と欠席日数には関連を示すデータがある」として、ツールを活用して、学校内の実態を把握しようとしている。それをもとに「授業の改善」や「学校環境の整備」などを進め、「みんなが安心して学べる場所にする」としている。学校のあり方を見直すことにもつながりそうだが、現場ではどう受け止められているのか…。
「新しいことを始めるのはいいことだが、どうやったらできるのかと考えてしまいます」。
そう話すのは、小学校教諭の女性(30代)だ。
かつて、担任をしたクラスの子どもが教室に入れず、別室に登校することが続いた。担任として、苦しんでいる子どもをケアしたい気持ちはあったが、自主学習用のプリントを用意するだけで精一杯だった。
「子どもたちのために、いろいろやりたいと、ずっと思っています。でも、時間も人手も足りません。学校に余裕があれば、別室登校の子どもたちを指導する先生を配置できます。でも、辞めてしまったり、長く休んでしまっている先生たちも多く、余裕のある学校は少ない」。
小中学校の教員をめぐっては、中学校では77%、小学校では64%を超える教員が、国が残業の上限としている月45時間を上回っていることがわかった。(文科省調査)
女性は自宅に仕事を持ち帰ることもあり、「今も無理をしてやっているところもあり、正直、身体がいつまで持つか分からない」と不安そうな表情を見せた。
■ 授業途中の休憩もOK 「学校らしくない学校」
不登校の子どもたちが行きやすい学校とはどんなものなのか。「子どもたちが落ち着いて過ごせる場所」を目指し、4月に開校したのが、宮城県白石市の「白石きぼう学園」だ。
小中一貫の「不登校特例校」で、廃校になった校舎を活用し、市が設置した。市内に民間のフリースクールがないこともあり、子どもたちの学びの場の選択肢を増やした。
「不登校特例校」は、不登校の子どもたちに合わせた特別なカリキュラムを組むことができ、国は全国に300校の設置を目指している。4月時点で、24校で子どもたちが学んでいる。
利用料のかかるフリースクールと違い、公立では授業料は無償で、他の学校と同じように卒業資格を得ることができる。
1時間目、中学1年の教室では子どもたちが理科の授業に取り組んでいた。学校指定の制服や運動着などはなく、それぞれが自由な服装で授業を受けていた。
授業の途中、「ちょっと行ってくる」と1人の生徒が、教室を出て行った。先生はどこに行くのかを確認したが、無理に教室に戻そうとはしなかった。また授業の途中から、登校してくる生徒もいた。
この学校では、授業時間は決めているものの、途中の休憩を認めている。また本人の体調や心の状態を尊重し、自由に遅刻や早退もできる。他の公立学校よりも授業時間数を減らし、自分の興味関心のある勉強ができる時間もあり、学び直しや苦手な内容にも対応しやすくなっている。
我妻聡美校長は「子どもたちのやりたいこと、子どもたちに合わせることを大事にしています」と話す。小学5年から中学3年まで19人の子どもたちが通っているが、子どもたちに変化を感じているという。
「何年も学校に行けなかったという子どもが、休まずに来てくれています。子どもたちは『難しいルールがない』と言って、学校を楽しんでくれています。明確な理由はまだ分からないのですが、先生方がゆったりとした姿勢で子どもたちを迎えることで、子どもたちに気持ちのゆとりができていると感じています」。
我妻校長は「ここで学んだことを他の学校にも活かせたら」とする一方、「少人数だからこそできることも多い」と話した。
増え続ける不登校の子どもたちが、安心して学べる環境をつくるための「受け皿」づくりは進んでいる。一方、不登校の子どもたちを「受け皿」で対応するだけでなく、子どもたちにとって、また負担のかかる先生たちにとって過ごしやすい学校をつくることも求められている。
テレビ朝日報道局 笠井理沙
広告
1
広告