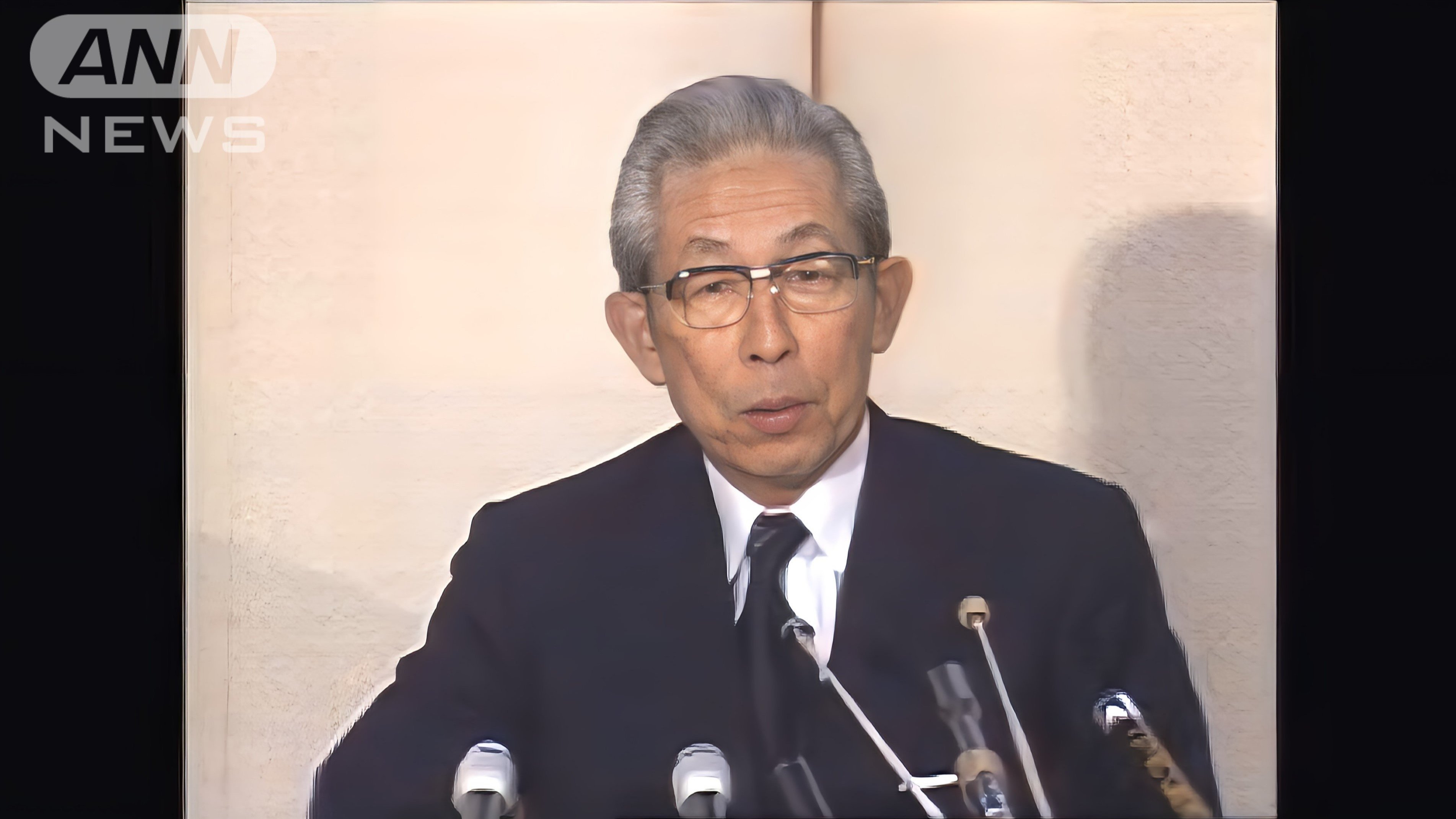円安に歯止めかからず… 日銀の利上げはありうるか
円安に歯止めがかからない。
最大の要因は内外とくに日米の金利差だ。日本が低金利(金融緩和策継続)でアメリカが高金利のため、日本からアメリカへマネーが流れる、円を売ってドルを買う。
金利差を小さくするには、アメリカが利下げするか、日本が利上げするか、2つしかない。ところがアメリカのFRB(連邦準備制度理事会)は12日、利下げについて年に3回という想定を1回だけに減らした。
そこで6月13日からの日銀の金融政策決定会合の結果に注目が集まる。
円安対策を念頭に置いた金融政策、とくに金利引き上げというのはありうるのか。
“アベノミクス”“黒田バズーカ”による大規模な金融緩和で事実上の超円安誘導が固定されて以降、なかなかその姿を想像できなくなった。
しかし円安防止を念頭に置いた金利引き上げは過去にあった。今から44年前、1980年だ。
イケイケ「経済大国」時代でも円安対策はあった
「円安防止へ緊急策」という新聞一面見出し。ここ最近の紙面のようにも見える。実際は1980年3月3日だ。
円安による通貨不安を回避するため、各国の通貨当局が協調介入を決めたことを伝える記事だ。
「円相場の下落を放置すれば本格的な通貨不安を招く恐れがあると各通貨当局が判断した」「大きく円安に傾いている円・ドル市場の空気を変えるため、ドル売り・円買いの市場介入を強化する思い切った対応策をとる必要がある、と判断したとみられる」(『朝日新聞1980年3月3日』)。
この年は円相場が年明けに1ドル233円台を付けてから下がり続けた。242円台に下落した2月中旬以降は、政府・日銀がドル売り円買いの単独介入を連日行った。
それでも抵抗線の250円を2月末に割り込み、国際的な協調介入で円を買い支える緊急策という事態に追い込まれたのだ。
円を主な対象とした協調介入は初めて、と報じられた。
1980年と言えば、世界のGNP(国民総生産)に占める日本の比重が約10%に達し、日本が「経済大国」になったとされる年だ。高校日本史の教科書にも太字で出てくる。前年に『ジャパン・アズ・ナンバーワン』も刊行されたばかりだ。少子高齢化もデフレもまだない。
そんな、いわば日本経済がイケイケだったと言える時代にも、急激な円安を契機に通貨不安・物価高への対策が必要だったのだ。
なぜイケイケ時代の経済大国なのに円安だったのか。
国際的なインフレや政情不安も背景にあったが、最大の要因は結果として日本の公定歩合は7.25%、それに対してアメリカ13%をはじめとする内外金利差があったためだ。
アメリカや西欧各国の高金利政策の狙いには高金利で自国通貨高を維持し、輸入インフレを弱めようという思惑も含まれていたとされる。
「以前のように為替レートの切り下げ競争で輸出を増やし、輸入を減らす方式を各国が採らないのは、それなりの理由がある。それは為替レートを切り下げるとその分輸入コストが高まって国内インフレが激化、長期的にその国の経済、対外競争力を弱めるという点が重視されるようになってきたからだ」(『日本経済新聞1980年2月18日』)。
実に44年前の指摘である。日本にはいまだに根強い“超円安信者”がいるが。
次のページは
通貨不安・物価高防止 日銀が公定歩合を最高の9%に通貨不安・物価高防止 日銀が公定歩合を最高の9%に
日銀は結局、1980年3月18日の政策委員会で、公定歩合をそれまでの7.25%から大幅に引き上げて、年9%とすることを決めた。
各国の通貨当局まで協調した円防衛策の実施後も、為替市場での円売り・ドル買い圧力は強く相場の不安定な状態が続き、政府・日銀は1週間で30億ドル近い円買いで支えていた。
円安の背景に日米の金利差が当面の理由となっていると認めざるをえない状況になった。
1979年中の3回と1980年2月に続く、第5次公定歩合引上げだった。特に前回1980年2月の第4次引上げから29日間という史上最短期間で、さらに9%は過去最高タイの「危機ライン」に達するものであった。異例づくめだった。
利上げの最大の目的は電気・ガス代値上げといった物価高の抑制とされた。ただ円安が物価高騰に、逆に円高が物価抑制に直結することは、当時から卸売物価や消費者物価のデータでも明らかになっていた。
そのうえでアメリカのインフレ対策による利上げ観測との綱引きの中、「円安ムード」を一掃する必要があったのだ。
利上げに対しては景気の先行きへの不安が出るものだが、経済界も「インフレ防止のためにはやむをえない」(経団連)、「米国などとの金利差を考えれば反対できない」(日商、日経連(後に経団連と統合)、経済同友会)と受け入れた。
通貨不安のリスクを回避する重要性
公定歩合引き上げ以降、円相場はさらに下がったあと、アメリカの公定歩合引き下げ13%→12%(5月29日)→11%(6月13日)→10%(7月25日)と軌を一にして円安を脱し、通貨不安を防ぐことになる。このような経験から円相場の歴史はアメリカの金融・為替政策の歴史と言われることがある。
ここまで見た1980年と現在とは事情が異なるという見方は当然だろう。日銀の政策決定過程や金融調節手段も変わっている。しかし類似点も少なくない。
日米金利差以外にも、たとえば1979年のソ連によるアフガニスタン侵攻に対して今はロシアのウクライナ侵攻がある国際情勢不安、1980年に50%前後値上げした電気・ガスも最近値上げ傾向だ。
また「経済大国」だった当時は金利の絶対的高さゆえに“天井”“打ち止め”という壁があったが、「デフレ脱却」を依然掲げる今は長く続いた金融緩和の後遺症がある。
そして何よりも当時以上に、現在の円安が物価高だけでなく通貨不安のリスクを抱えているということである。
1990年代以降、メキシコ危機(テキーラ危機)、アジア危機、ロシア危機などが起きた。トルコ・リラの現状もそれに近い。日本の経済競争力低下と財政悪化が著しい今、外貨準備があるとは言え、通貨不安は起きないという思い込みはすべきではないだろう。
円安が急加速して通貨不安が現実化した場合、最終的に止められるのは協調介入をはじめとした国際的な支援しかない。その場合は景気判断を見切った大幅金利引き上げだけでなく財政支出の見直しまで余儀なくされる可能性がある。何よりも食料・エネルギー自給率の低い日本には相当きつい。
そのリスク削減をアメリカの金融・為替政策待ちに委ねるわけにはいかない。
金融当局者は「通貨不安」を表立って口にすることはない。その瞬間に火が付くおそれがあるからだ。
ただ通貨不安のリスクを少しでも減らすために、日銀は、予防的な物価抑制の名目を借りても、少なくとも利上げの方向性のメッセージを発しておくべきではないか。そういう時機が来ていると思う。
(テレビ朝日デジタル解説委員 北本則雄)