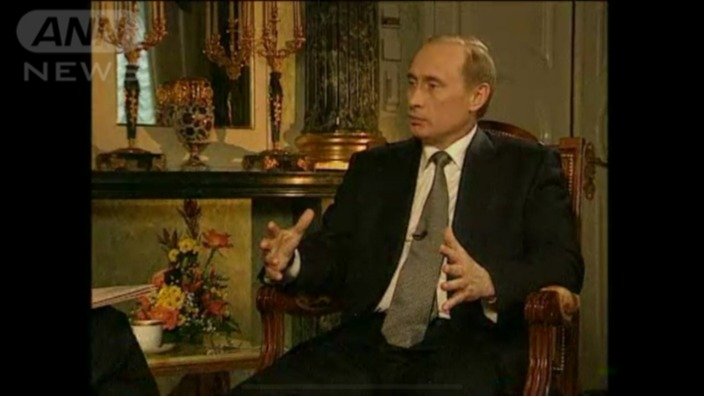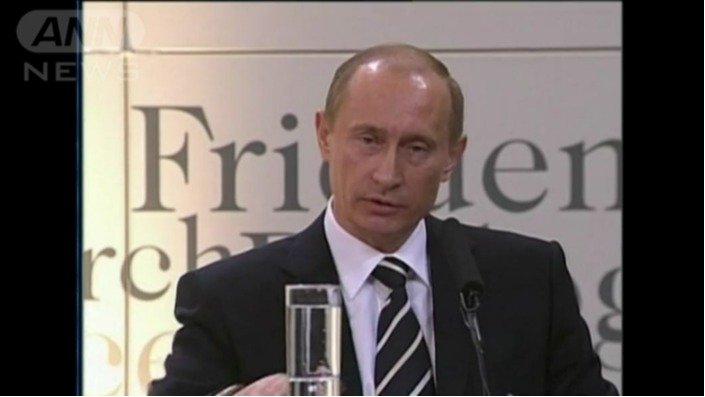アメリカ・トランプ政権のウィトコフ特使が11日、ロシア入りし、プーチン大統領とも会談した。
米ロ外交筋によればトランプチーム内では、米ロ首脳会談で交わす合意内容を11日までに仕上げるよう指示が出ていたというから、ギリギリのタイミングでの訪ロということになる。
ただ、米ロ首脳会談の実現に向けては両者の溝が深過ぎ、戦争は継続、トランプ政権がロシアに新たな制裁を科すところまで行きつくという悲観論もささやかれている。
ウクライナ戦争の停戦交渉に関わるクレムリンに近い関係者から、先月届いたメッセージは、想像していたよりも激しい内容だった。
関係国を飛び回っている彼に米ロ交渉の現状について尋ねていた。返信のメッセージは、こう続く。
プーチン大統領はトランプ大統領との停戦交渉で何を実現しようとしているのか。到底妥協点が見い出せない交渉をロシアが続ける理由はどこにあるのか。探っていくと、プーチン大統領の25年におよぶ欧米への復讐劇を完結させようとする狙いが浮かび上がってくる。
(ANN取材班)
ウクライナという国家を否定するプーチン
ロシアがウクライナの解体を目指しているという内容の正しさが裏付けられたのは、メッセージを受け取った翌日の3月27日だった。
プーチン大統領は、北極圏のムルマンスクを訪れていた。そこで原子力潜水艦「アルハンゲリスク」の船内で水兵らと会談した際、ドームニンという名の二等兵から質問を受ける。
プーチン大統領は低い声ですごんだ。
冗談のつもりだったようだが、その場に居合わせた数人の乗組員は一切笑わなかった。むしろ、どう反応してよいか分からないようで、表情は引きつっている。
凍り付いた雰囲気を気にすることもなくプーチン大統領は、現状のままではゼレンスキー政権とは交渉すらできないといい、こんな持論を展開する。
これまでもプーチン大統領は、「戒厳令」を理由に大統領選挙を行っていないゼレンスキー氏には大統領としての正当性がないと主張してきた。
今回はさらに踏み込み、ウクライナの統治機構そのものが正当性を失っていると言い出した。国自体が違法状態だから、大統領選を行ったとしても、その結果を認めないという。極端な主張だ。
その上で、次のような要求を提示する。
西側諸国と緊密な関係を築くゼレンスキー大統領の影響力を完全に無くし、ロシア寄りの政権を樹立しようとしているのだろう。
トランプ政権との交渉開始で要求はエスカレート
プーチン大統領は、本格侵攻当初からウクライナの主権を無視する発言を繰り返していて、ウクライナの完全消滅を目標にしてきたとみられるが、はっきりとは示さなかった。実現にはさらなる動員が必要で、ロシア社会の反発や混乱が予想されるからだろう。「ウクライナの『非ナチ化』」というあいまいな表現に留めていた。
ところが、トランプ政権がロシア軍占領地の承認やウクライナのNATO非加盟の確約など、ロシア寄りの提案を並べ、停戦に合意するよう「取引(ディール)」を打診すると、プーチン大統領は領土に留まらずウクライナ内政や軍事支援の停止、制裁解除など要求を増やし、ついにはウクライナという国家の存在まで否定するよう求め出したのだ。
プーチン大統領に交渉を成立させようとする姿勢は一切見られず、少しでも有利な落とし所を探る交渉上のテクニックとは違う。それどころか交渉を暗礁に乗り上げさせようとしている。
プーチン大統領は、停戦交渉について語るとき、意識的に中国やインドなどに言及している。さらに3月27日には北朝鮮まで名前を挙げた。
多くの国を関与させれば、交渉はより複雑になり、成立は遠のく。プーチン大統領の言動からは「停戦」を成立させようという熱意はみじんも感じられない。
「怒る」トランプ大統領
ロシア寄りだったトランプ氏も態度を豹変させる。
3月30日、アメリカメディアはトランプ氏が「非常に怒っている」「腹を立てている」と報じる。トランプ氏とゴルフをし、率直な会話を交わしたフィンランドのスタブ大統領は「私の感触ではトランプ大統領は、ロシアに対する忍耐が尽きかけているようだ」とメディアに証言した。
トランプ大統領は、ロシアが停戦合意に否定的だと判断した場合、ロシアから輸出される石油に最大50%の二次関税を課すと脅した。さらに超党派の上院議員グループは、ロシアの石油、ガス、その他の資源を購入する国に500%の二次関税を課す法案まで作成した。
クレムリンに近い関係者は、新たなエネルギー制裁はロシア経済にとって危機的なものだと打ち明ける。
にもかかわらず、プーチン大統領が停戦をするつもりはないとみている。
なぜ「停戦」をする気がないにもかかわらず、プーチン大統領は、トランプ政権と「交渉」をするのだろうか?それは単純に新たな制裁を回避するためだけではない。
前述した潜水艦のドームニン二等兵が戸惑うように、長年にわたって「最大の敵」だと位置づけられてきたアメリカとの接近はプーチン支持層にとって理解ができないものだ。
だがプーチン大統領と欧米との25年にわたる関係を振り返ると、その答えが浮き彫りになる。
ヨーロッパにあこがれ、裏切られたプーチン大統領
2000年3月、プーチン氏はBBCの名物司会者デイビット・フロスト氏のインタビューで、今では考えられないようなヨーロッパへの想いを告白している。この時、プーチン氏はロシアをヨーロッパの一部として考え、ヨーロッパと共に発展する道を描いていたようだ。
KGBのスパイとして家族と共に東ドイツに長く暮らしたプーチン氏は、ドイツ連邦議会で流暢なドイツ語で演説するなど欧米への愛着を隠さなかった。
しかし当時、NATO=北大西洋条約機構に1999年にハンガリー、ポーランド、チェコが加盟し、ロシアと欧米は緊張関係にあった。
そこでフロスト氏は、「ロシアが NATO に加盟する可能性はあるのか?」という突っ込んだ質問をする。プーチン氏はこう答える。
プーチン氏はNATOにロシアが加盟する意向があると表明する。その真意は明らかではない。もしかしたら内部から解体しようと考えていたのかもしれない。ただ、少なくとも欧米と接近する方法を模索していたようだ。
もちろんロシアのNATO加盟は実現せず、2004年にはバルト三国をはじめルーマニア、スロバキア、スロベニア、ブルガリアの7カ国が加盟した。NATOの「東方拡大」は、ロシアを牽制しようとするものではなく、むしろロシアに脅威を感じた国々が自国の安全保障のためにNATOの力に頼った側面が強い。
しかし、プーチン大統領の認識は違った。欧米に裏切られたと捉えた。
プーチン大統領が抱えるアメリカへの“復讐心”
ロシアがヨーロッパの一部になろうとする試みは終わり、2007年の有名な演説につながる。
2007年2月10日、プーチン大統領はミュンヘン安全保障会議の場で初めてNATO拡大に対するロシアの憤りについてためらうことなく語った。そして怒りの矛先はアメリカ中心の「一極支配」に向けられる。
「カラー革命」「アラブの春」と呼ばれた旧ソ連圏と中東の民主化運動も、プーチン大統領にとっては、欧米諸国によるロシアへの挑戦だった。
セルビア、ジョージア、ウクライナ、キルギスといった旧ソ連圏の権威主義国家の君主は次々と反体制派に打倒され、民主的な政治体制に塗り替えられた。プーチン大統領は、欧米諸国が各国の反体制派に資金を投じ、ロシアを崩壊させようとしているものだと認識する。
反体制派を欧米諸国が支援した側面もあるが、多くの人が街に繰り出したのは独裁体制への不満が限界に達していたからだった。
しかしプーチン氏は欧米への不信を募らせる。2011年4月27日。コペンハーゲンを訪れたプーチン首相(当時)は、リビアの反体制派を支援しカダフィ政権に対して空爆を開始した欧米に怒りを露わにする。
ロシア国内に対しても「民主化運動」を推進する反体制派は、欧米諸国が操っていると信じこみ、プーチン氏は首相から大統領に復帰した2012年、「外国代理人」を規制する法律を導入する。外国から資金提供などを受けた組織や個人を「スパイ」だと認定し、活動を制限するのだ。
ウクライナ侵攻と「停戦交渉」の本当の狙い
2022年2月24日未明に放送された、ウクライナへの「特別軍事作戦」の開始を告げるテレビ演説は、こうした欧米への怒りからはじまる。
ウクライナへの大規模侵攻は、欧米への復讐心が根底にある。そしてアメリカという大国による一極支配を打ち崩そうとする野心がプーチン氏の原動力となっている。
トランプ氏との「交渉」をこの復讐劇の一部だと捉え直すと、なぜプーチン大統領が停戦する気もないのにトランプ氏と交渉を続けているのか、答えが浮かび上がってくる。
アメリカがロシアの主張を受け入れざるを得ない状況を作り出し、アメリカの衰退を決定づけたいのではないだろうか。あるいは停戦交渉を失敗に終わらせ、トランプ政権がいかに仲介能力を持っていないかを世界に見せつけることが、プーチン氏にとっての「交渉」の狙いだとみるべきなのではないだろうか。
少なくとも、アメリカの影響力の大きさを裏付けるようなことになる停戦の実現をプーチン氏が後押しすることはないだろう。