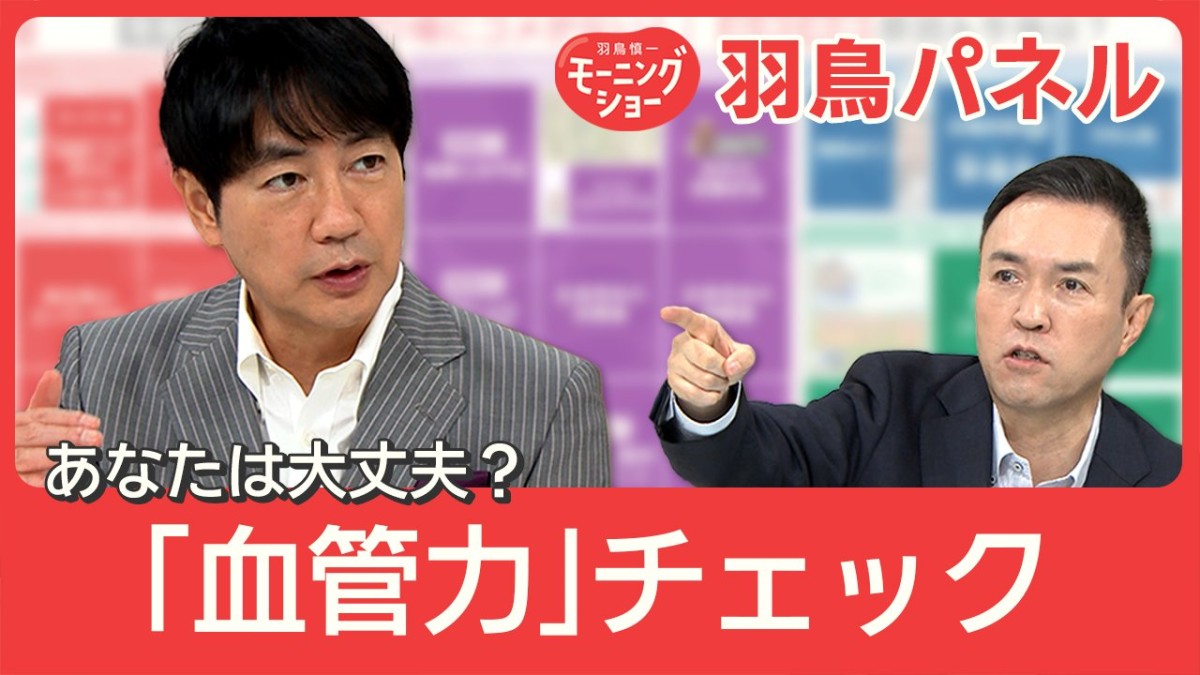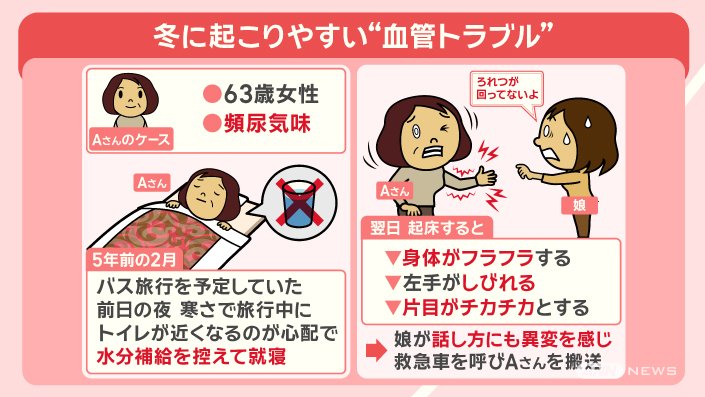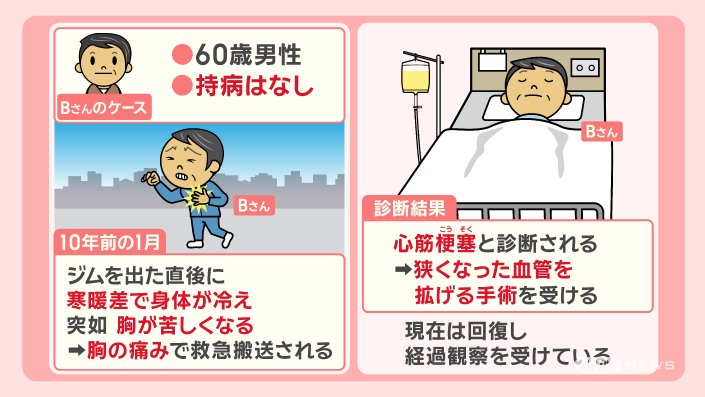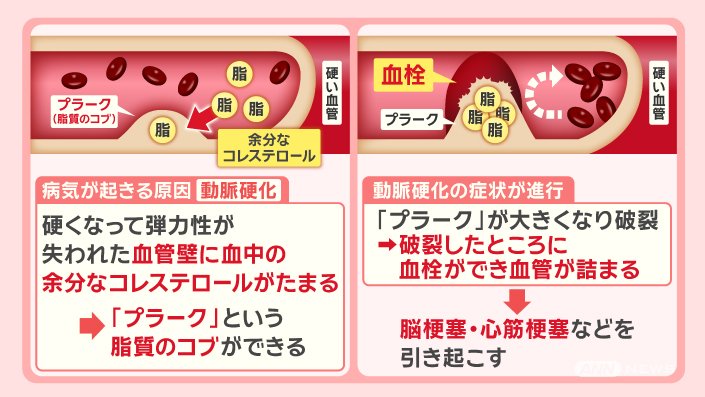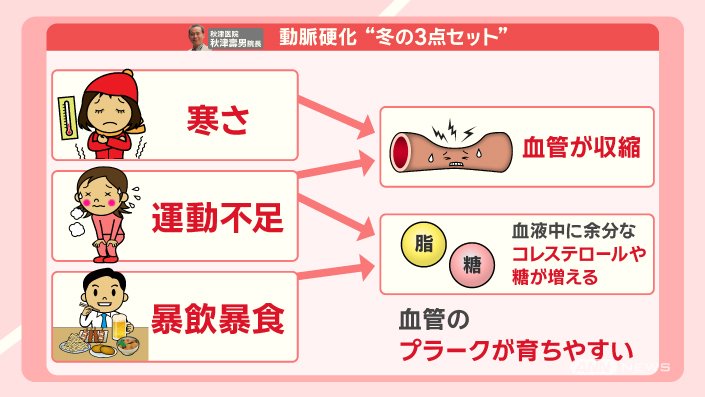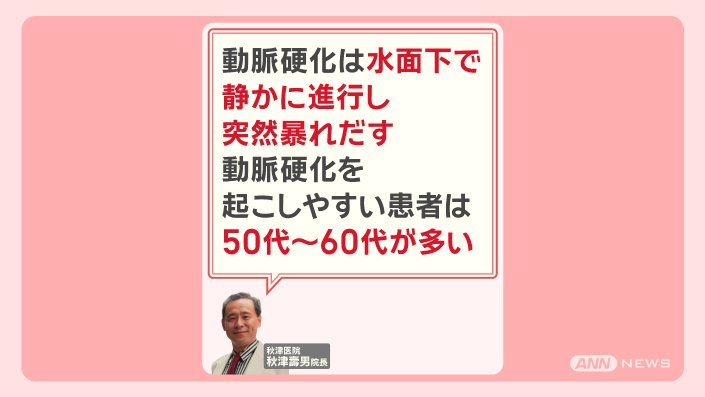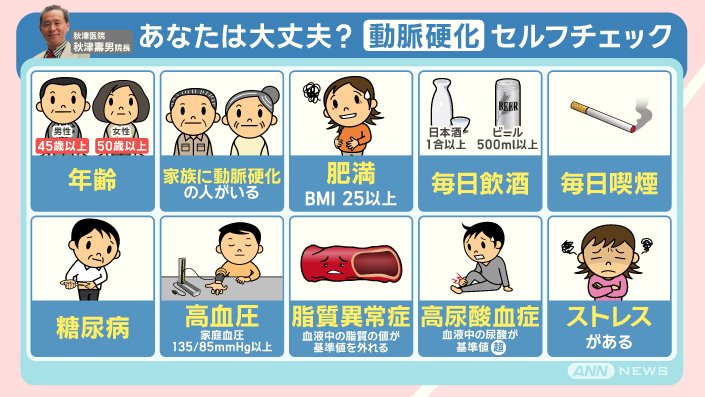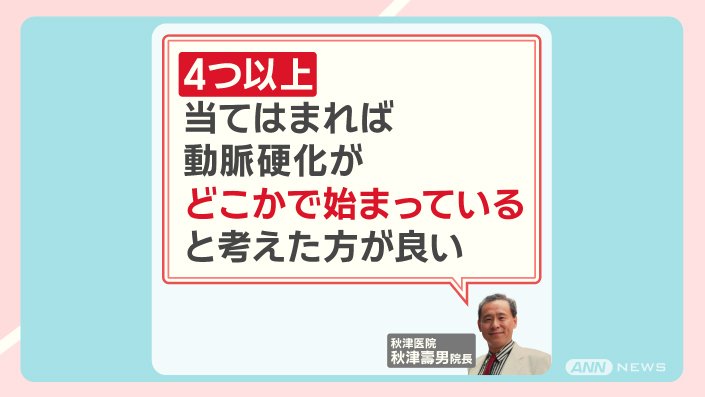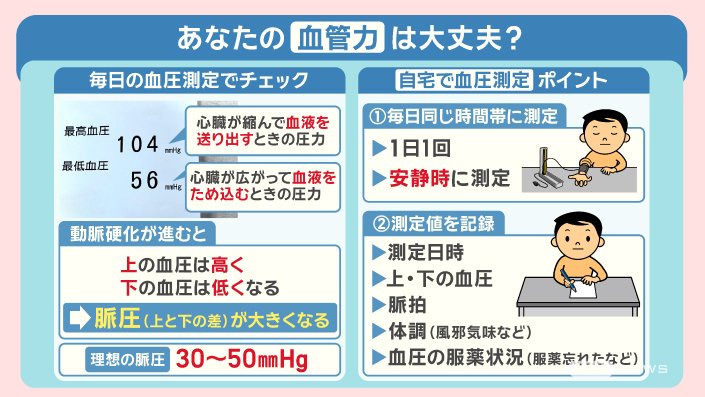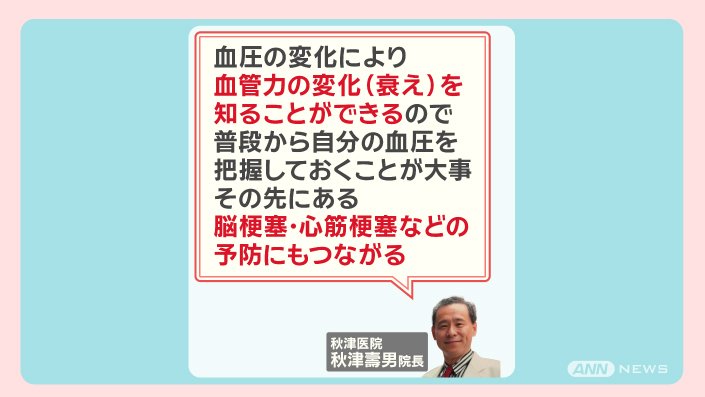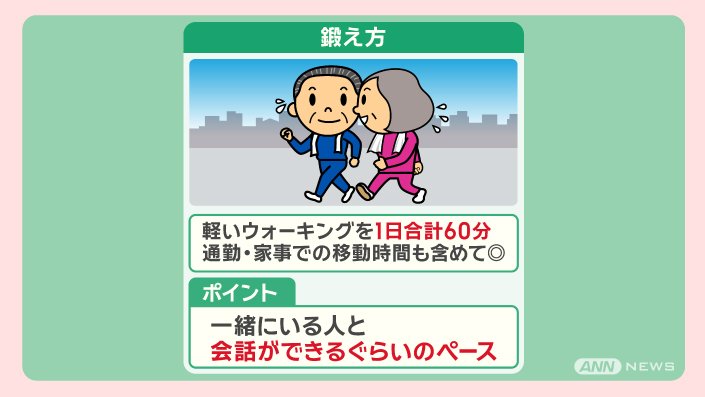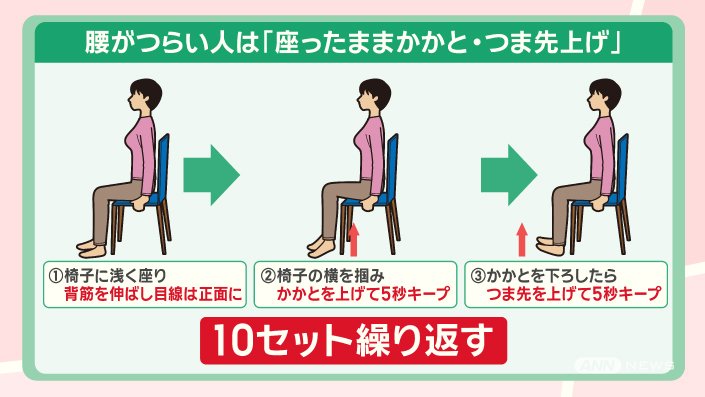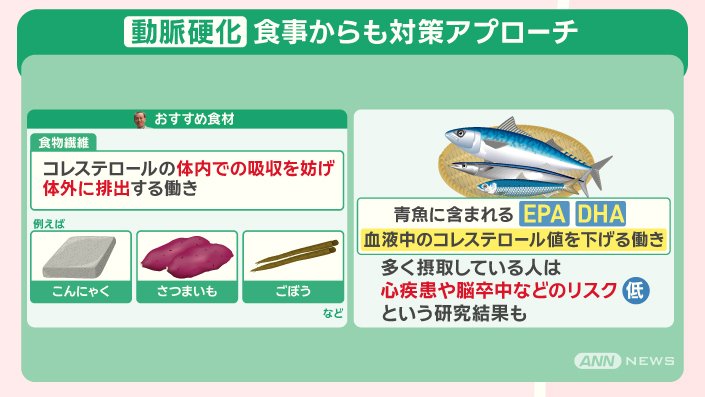今シーズン最強の寒波の影響で、各地で厳しい寒さとなっています。
今の時期、動脈硬化に注意が必要です。
■なぜ?冬に多発する動脈硬化 死亡リスクも
冬に起こりやすい“血管トラブル”です。
Aさんは63歳の女性で、頻尿気味ということです。
5年前の2月、バス旅行を予定していた日の前日の夜、寒さで旅行中にトイレが近くなることを心配して、水分補給を控えて、寝ました。
翌日、起床すると、身体がフラフラとし、左手がしびれ、片目がチカチカしました。
同居している娘さんが「ろれつが回ってないよ」と言うくらい、話し方にも異変を感じたそうです。救急車を呼び、Aさんは病院に搬送されました。
搬送先の病院で、脱水症状が引き金となり、軽い小脳梗塞を発症していると診断されました。
Aさんは、一晩入院して点滴治療を受け、その後回復しました。
Bさんは、60歳男性で、当時、持病はありませんでした。
10年前の1月、ジムを出た直後に、寒暖差で身体が冷え、突如、胸が苦しくなり、救急搬送されました。
病院で、Bさんは、心筋梗塞と診断され、狭くなった血管を拡げる手術を受けました。
現在は回復し、経過観察を受けています。
脳梗塞や急性心筋梗塞の月別の死者数です。
1年を通して見ると、両方とも、冬になると亡くなる方が増加します。
脳梗塞および急性心筋梗塞の原因となる動脈硬化についてです。
健康な血管は、弾力性があり、やわらかく、血管壁の内側の壁がなめらかなので、血液がスムーズに流れています。
病気が起きる原因となる『動脈硬化』は、硬くなって弾力性が失われた血管壁に、血中の余分なコレステロールが入り込みたまることで、『プラーク』という、脂質のコブができます。
さらに症状が進行すると、『プラーク』のコブは大きくなり、破裂します。
破裂したプラークの傷口に血栓ができ、血管が詰まります。
その結果、脳梗塞や心筋梗塞などが引き起こされます。
動脈硬化がもたらす病気は、脳梗塞、心筋梗塞、狭心症、大動脈瘤などです。
特に冬は、動脈硬化を起きやすくする『冬の3点セット』があるといいます。
『寒さ』『運動不足』『暴飲暴食』です。
『寒さ』や『運動不足』で血管が収縮し、『運動不足』や『暴飲暴食』で、血液中に余分なコレステロールや糖が増えます。
その結果、血管壁にあるプラークが育ちやすくなります。
「動脈硬化は、水面下で静かに進行し、突然暴れだす。動脈硬化を起こしやすい患者は、50代〜60代が多い」ということです。
次のページは
■動脈硬化 注意が必要な人は?「血管力」チェックで予防も■動脈硬化 注意が必要な人は?「血管力」チェックで予防も
動脈硬化を自分でチェックしてみましょう。
チェック項目は10個です。
<1>年齢 男性は45歳以上、女性は50歳以上である。
<2>家族に動脈硬化の人がいる、または動脈硬化がきっかけの病気(脳梗塞・心筋梗塞・狭心症・大動脈瘤など)を患ったことがある人がいる。
<3>肥満(BMIが25以上)である。
<4>毎日、飲酒している。(日本酒なら1合以上、ビールなら500ml以上)
<5>毎日、喫煙している。
<6>糖尿病である。
<7>高血圧である。(家で測る血圧が、上135mmHg、下85mmHg以上)(病院の診察室で測る血圧が、上140mmHg、下90mmHg以上)
<8>脂質異常症(血液中の脂質の値が基準値を外れる状態)と医師に診断された、または健康診断で判明した。
<9>高尿酸血症(血液中の尿酸が基準値を超える状態)と医師に診断された、または、健康診断で判明した。
<10>ストレスがある。
「4つ以上当てはまれば、動脈硬化がどこかで始まっていると考えた方が良い」ということです。
そして、日常生活でこんなことがあると要注意です。
これは、足の動脈硬化の可能性があります。
日常生活の要注意、2つ目です。
これは、心臓の動脈硬化の可能性があります。
日常生活の要注意、3つ目です。
これは、脳の動脈硬化の可能性があります。
大事な『血管力』のチェックです。
毎日の血圧測定でチェックできます。
最高血圧は、心臓が縮んで血液を送り出すときの圧力、最低血圧は、心臓が広がって、血液をため込むときの圧力です。
動脈硬化が進むと、血管の弾力性が失われて、上の血圧は高く、下の血圧は低くなり、上と下の差である『脈圧』が大きくなります。
理想の脈圧(上と下の差)は、30〜50mmHgです。
脈圧は、大きすぎても小さすぎても、良くないということです。
自宅で血圧を測る際のポイントです。
毎日同じ時間帯に測ります。
▼1日1回
▼安静時に測定
測定値を記録しておきます。
▼測定日時
▼上・下の血圧
▼脈拍
▼風邪気味など、その時の体調
▼服薬の状況(血圧の薬を飲んでいるなら、飲むのを忘れたなど)
「血圧の変化により、血管力の変化(衰え)を知ることができるので、普段から自分の血圧を把握しておくことが大事。その先にある脳梗塞・心筋梗塞などの予防にもつながる」
■動脈硬化の予防 「第二の心臓」ふくらはぎ鍛えて血管力アップ
動脈硬化の予防方法です。
「動脈硬化の予防には、あまり激しくない、適度な有酸素運動が有効。血管の周囲の筋肉を動かすと、血管がほぐれて、柔らかくなる。また、動脈硬化の原因のプラークもできにくくなる」ということです。
特にカギとなるのが、『第二の心臓』と呼ばれるふくらはぎです。
ふくらはぎは、収縮と弛緩を繰り返すことで、全身の血液循環を促している筋肉なので、ふくらはぎを鍛えて、血管を柔らかくすることが重要です。
では、ふくらはぎをどう鍛えればよいのでしょうか。
軽いウォーキングを1日合計60分するのが、おすすめです。通勤や家事での移動時間も含めて大丈夫です。
ポイントは、一緒にいる人と会話ができるぐらいのペースで行うことです。
さらに、室内でも簡単にできる、動脈硬化予防のふくらはぎの筋トレ法です。
『スロースクワット』です。
<1>まず、足を肩幅より少し広めに開き、椅子の背もたれを掴みます。
<2>5秒かけて、膝が90度になるまで腰を落とします。つらい人は中腰でも大丈夫です。
<3>腰を落としたら、5秒姿勢をキープ。
<4>その後、5秒かけて、ゆっくり元の姿勢に戻ります。
これを10セット繰り返します。
腰が辛い人には、『座ったままかかと・つま先上げ』がおすすめです。
<1>まず、椅子に浅く座って、背筋を伸ばし、目線は正面に向けます。
<2>次に椅子の横を掴み、かかとを上げて5秒キープ。
<3>かかとを下ろしたら、今度はつま先を上げて5秒キープします。
これを10セット繰り返します。
動脈硬化の食事の面での対策です。
秋津院長おすすめは、『食物繊維』です。
コレステロールの体内での吸収を妨げ、体外に排出する働きがあります。
例えば、こんにゃくや、さつまいも、ごぼうなどです。
他にも、動脈硬化予防に、青魚が良いということです。
青魚に含まれる『EPA』『DHA』には、血液中のコレステロール値を下げる働きがあります。
これらを多く摂取している人は、心疾患や脳卒中などのリスクが低下したという、研究結果もあります。
(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年2月4日放送分より)